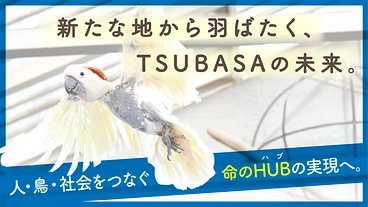支援総額
目標金額 2,000,000円
- 支援者
- 92人
- 募集終了日
- 2022年8月31日
【終了まで残り6日】フードバンクにかける私たちの「想い」
日頃よりフードバンクさがの活動にご支援いただきありがとうございます。
今回、レディーフォーのクラウドファンディングに挑戦しておりますが、いよいよ残り6日間となりました。
現在、35名の方から計57万円のご寄付をいただいております。ご支援いただいた皆様には深く御礼申し上げます。
ただ、目標の200万円はまだまだ遠く、広くご寄付いただくことの難しさを実感している次第です。
実は、クラウドファンディングに挑戦するのは二度目です。
昨年、夏休み・冬休みの給食が無い期間に小中学生にお弁当を届ける「お弁当プロジェクト」で佐賀県ふるさと納税ガバメントクラウドファンディングに挑戦し、目標額を大きく上回るご寄付をいただきました。
「お弁当プロジェクト」はこの夏休みに約1,700食を提供し、非常に助かったとの声をいただきました。今後は冬休みに向けて準備を開始しています。
中間支援団体の難しさ
コロナ禍でもあり、こういった直接支援事業は非常に喜ばれていますが、一方でフードバンク事業そのものは原油価格の高騰や需要の拡大もあり、運営は非常に厳しい状況です。「誰か」に「何か」を「買って」届ける事業ではなく、地道な寄贈元へのお願いや提供先団体のニーズ把握、衛生管理の徹底などが求められるフードバンク事業は中間支援でもあり、その運営費を支援いただく今回のクラウドファンディングはなかなかアピールが難しいなと感じています。
事業規模は拡大したけれど・・・
助成事業は多くやらせていただいており、事業規模は大きくなっていく一方で残念ながら運営費に利用できるものは少なく、やはり皆様のご寄付が「いのち綱」です。
今後の事業継続に悲観的な意見もでる一方で、昨年度約30,000人に食品を提供する団体にまでなった以上その影響も大きく、お金がないからやめるということは出来ないと考えています。
であれば、自分が無償で汗をかくだけでなく、「寄付金をください」とお願いする責任が私たちにはあると考えています。
フードバンクさがの中心である事務局スタッフの想いをお伝えします。
理事長 干潟由美子
クラウドファンディングへのおもい
フードバンク活動が全国でも広がりをみせていますが、わたしたちが任意団体としてフードバンクを立ち上げたのは2019年3月でした。2020年12月に法人格を取得し今年4年目を迎えました。
【なぜフードバンクだったのか】
私は、15年ほどスーパーに勤務していました。食品を扱うという仕事柄、お客様に「おいしい」を届けたいという思い、手に取って購入してくれたときの「ありがとうございます」という思い。
そんな仕事が大好きでした。でも、どうしても廃棄しなければならないものがあるのも事実です。
また、農産品の生産者の方々とのおつきあいもあり、野菜ひとつをつくるにも、畑の土づくりから始まり、大事に、大事に手間暇かけられてつくられたお野菜も、天候次第では、病気になって収穫できないことがあることも。消費者にもっと手にとって食べてほしいという思いから、野菜作りに精をだされても、調理方法がわからない等、どうやったら食べてもらえるのだろうという悩みも伺っており、そんな過去の経験が頭の片隅にずっとありました。
そうかといって、私自身が食品ロスを出さない生活ができていたのかといえば、できていないことのほうが多かったように思います。
【フードバンクを立ち上げる覚悟】
そんな私が2017年、「フードバンク」という活動を詳しく知ることになります。
「食」で人と人をつなぐ活動。ここからわたしの活動がスタートしました。
先駆的な取り組み事例を聞いたり、施設の見学に行ったり、他県のフードバンクでボランティアとして受け入れてもらいながら、フードバンクの仕組みの作り方、運用の仕方などを学ばせていただきました。背中を押してくれたのは、まわりのたくさんの人。「頭で考えるよりも動きながら考えればいい」その言葉に何度勇気をもらったことか。
最初は食品ロスをどうにかしたいと考えていた私ですが、様々な方々とつながっていくうちに社会の中で今起きていること、いろんな課題がたくさんあることに気づかされます。
こどもの貧困や女性の貧困がそのひとつです。
【見えない貧困】
地域の中で、フードバンク活動のお話をさせていただく機会がありますが、「うちの地域にはそんなこども(家庭)はいないよ。」という声をお聞きすることがあります。
今、6人に1人のこどもが「相対的貧困」状態に置かれているといわれています。
物・人と人とのつながり・子どもの成長に欠かせない様々な経験が奪われているのだとしたら、わたしたちは「食」という入口から何かできることはないだろうかと考えました。
【フードバンク活動は手段である】
フードバンクというと、食に困っている方々のために食品を集めて、右から左へ渡しているだけとおっしゃる方もいらっしゃいますが、寄贈してくださる方々、食品を提供する団体から更に必要としている個人の方々へ。そこにはどれだけの「人」が関わってくださっているでしょうか。
私たちは食品を循環させる仕組みをつくりましたが、その仕組みを活用してくださる方々がいなければ、フードバンクという活動は続けていくことはできなかったでしょう。
昨年度は33,800人の方へ45㌧の食をお届けすることができました。
皆さま一人ひとりの力がフードバンクを大きく成長させてくださっています。
【つないだ手を離さない】
個人の方へ直接食の提供はお断りしています。
中途半端な気持ちで向かい合っても、繋いだ手をはずしてしまえば、二度とつながることはないと考えるからです。
だからこそ、地域の福祉活動団体等を心から信頼して食を託しています。
それでも相談の電話やメールが届きます。
「数日食事をとっていません」等、困りごとを抱えている方の背景には様々な問題がもつれた糸のようにからまっていることがあります。
そのもつれた糸を丁寧にほぐしながら解いていってくれる人たちがいます。
フードバンクでは、駆け込み寺の役割は担えても、私たちができることは本当に少ないのです。
でも、繋いだ手を次に繋いでくれる人へ手渡しすることはできます。
たとえ手が離れても、完全に切れたわけではありません。次に繋いだ人と私たちは必要なときには、いつでもつながっていける関係だから。
だからこそ、私たちは中間支援組織として、自分たちの役割に専念することができています。
【それぞれの役割】
食を取り扱うフードバンクは、通常の流通とは違った仕組みの中で食品をお届けしています。
だからこそ、食への思いは人一倍熱いです。
寄贈するにあたって、企業や団体様が懸念されている食品の取り扱いでは、品質管理や衛生管理には充分配慮しています。
それは、食の生産段階からつないできてくださった「食の安全のバトン」を最後に食べる方まで安全・安心にお届けすることがわたしたちの役割だと考えています。
【わたしたちの活動を応援してください】
これまでの3年間、会員のみなさまのご支援や多くの方々からのご寄付をいただいて、活動をすすめてきました。
1年目の取扱量が5.5tだったのに比べ、昨年は45tを取り扱える団体になることができました。
取扱量が増えるにつれ、運営は厳しくなり、食品の運搬や燃料費は各自の持ち出しです。
食品を適正に扱うために、倉庫や冷凍冷蔵庫などの設備投資も必要です。
それでも、動けているのは「困ったときはおたがいさま」といえる社会をつくっていきたいから。
わたしたちの住むまちが、将来にわたって「誰もが住み続けられるまち」になることを願って。
【わたしたちのめざす姿】
人と人とのつながりや、参加の機会を生み育む多様な活動を通して、これまでとは異なる新たなご縁が生まれています。
その中には特定の課題の解決を念頭に始まる活動だけではなく、参加する人たちの興味や関心から活動が始まり、それが広がったり、横に繋がったりしながら関係性が豊かな活動をすることができました。
地域住民や地域の多様な主体が関わることで、人と人、地域資源と人をつなげていく重層的な支援の輪の中に、利用しやすいライフラインとして地域に根差し、「食」を入口として公的な支援につなぐことができる役割を担っていけるよう、活動をすすめてまいります。
副理事長 桑原廣子
子どもたちの笑顔あふれる未来のために
「日本の子どもの6人に1人が貧困」というニュースを聞いたときはとてもショックでした。もちろん子どもだけで貧困になるわけでもなく、それだけ多くの人が貧困状態にあるということですが。でも正直それを実感として感じることはできませんでした。縁あってフードバンクさがの立ち上げから活動に参加しています。
日々の活動の中、子ども食堂や子どもの居場所を開催されている団体や生活自立支援団体の方々から、困難な状況に置かれている方や子どもたちの生活の一端をお聞きすることもあり、胸が苦しくなるようなこともあります。冬休みに実施したお弁当プロジェクトで、お弁当を家庭に届けるお手伝いをさせていただきました。出迎えてくれる子どもたちが笑顔で待っていてくれて、別れ際に折り紙を手渡してくれた子もいました。
生まれた環境によって将来が左右されないよう、子どもたちみんなが未来に夢をもって生きていけるような社会にならなければと感じる毎日です。
コロナ禍の中、困難な状況に置かれた人たちは増える一方で、最近の物価高の影響でしょうか、食品寄贈の提案は頭打ちの状況です。フードバンクさがはまだ小さな組織ですが、3年間の活動を通じてつながっている人たちとの手を放したくないと強く思っています。子どもたちの笑顔あふれる社会の実現に、フードバンクもその役割を果たしていきたいと考えています。
事務局長 鍋田博
持続可能な社会システムとしてのフードバンクに支援の輪を!
福岡県で子どもが餓死で亡くなった。2020年4月、5歳の男の子が餓死したのである。亡くなる前に発した言葉が裁判の中で明らかにされ、呼吸が止まる数時間前に「ママごめんね」と最後の言葉を発したのである。亡くなる前に、どうしてそのような言葉を発したのか。母親をどうして許す言葉を発したのか。怒りとともにこのような不条理を許すことはできない。
子どもは親を選べない。子どもが救いを求める居場所はなかったのか。母親が相談する居場所はなかったのか。実に残念である。
今、新型コロナで居場所をなくした人が増加している。そこにロシアによるウクライナ侵攻である。
多くの物価が高騰している。生活に困窮する人たちが増えるのは確実だ。
多くの困難を抱える子どもたちが生み出されている。子どもから「助けて」と訴えることは本当に困難である。周りの大人たちが気づいたら少しでも「おせっかい」をし、子どもがいつでも来れる「居場所づくり」が必要だ。また、親についてもいつでも相談ができる「居場所づくり」が必要だ。
全国のフードバンクは、「フードバンクこども応援全国プロジェクト」として、個人宅へ宅配を行っている。その取り組みを通じて、子どもたちも、親たちも相談できる体制を準備しようとしている。「少しのおせっかい」で、命の危機を救おうとしている。
コロナ禍により日本でも貧困が重度化している一方で、日本はフードバンクの普及が遅れている。全国各地のフードバンク団体は、支援用の食品やノウハウ、運営費の不足など共通の課題を抱えている。これらの課題が団体の成長を阻害しており、食品ロスや貧困問題の社会的課題の解決手段としての役割を十分に果たせていない。
私たちは、このようなフードバンクが抱える課題を解決することにより、より多くの食料支援を困窮する世帯やその子どもたちに届けられるよう活動に取り組んでいく。そのための活動資金として今回クラウドファンディングに取り組んでいる。
事務局員 石原太郎
食品ロスと地域福祉とは
私は以前、NPO法人さが環境推進センターにお世話になっており、佐賀市から委託を受けている「佐賀市エコプラザ」に9年ほど勤めておりました。エコプラザは佐賀市清掃工場内にある環境学習施設です。3Rの推進やごみ減量、工場見学案内など行っておりました。
工場見学では、佐賀県内全域の小学生が訪れ大量のごみに驚き、時にはその「におい」にブーイングが出たりしていました。その時にお話ししたのは、ここのごみは皆さんの家から集まった物だし、「におい」だって皆さんのおうちの生ごみのものですよ、とお話ししていました。家庭から出る可燃ごみの約2割は生ごみです。その中には多くの手つかず食品が含まれていました。
一方で引率の先生たちからは、学校給食しかちゃんとした食事がとれず、栄養面が心配な子がいるのに…との感想もこういった食品ロスについていただいていました。
いくつかのきっかけと出会いがあり、今はフードバンクで事務局を務めておりますが、食品ロス削減と地域福祉の向上をどうつなげていくかは今も試行錯誤しております。
支援と自立の関係、環境負荷と商習慣の関係など学ぶことが山積しています。変えていかなければならないことも多々あると思います。
ですが「フードバンク」は地域の緩やかなライフラインとして、空腹を我慢し続けている子どもたち、声を挙げづらい大人たち、そういった人たちのために長く続ける価値があると信じています。皆様のお力が必要です。どうぞご支援をお願いたします。
最後に
スタッフそれぞれのバックグランドがありフードバンクにかける想いもそれぞれですがフードバンクが地域に必要だと信じて活動しています。皆様の想いに重なる部分があると思います。
最後まであきらめず頑張ります。どうぞ最後までご支援をお願いいたします。

リターン
5,000円+システム利用料

5千円寄付コース
・お礼のメール
・活動報告書
- 申込数
- 31
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2023年6月
10,000円+システム利用料

1万円寄付コース
・お礼のメール
・活動報告書
- 申込数
- 44
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2023年6月
5,000円+システム利用料

5千円寄付コース
・お礼のメール
・活動報告書
- 申込数
- 31
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2023年6月
10,000円+システム利用料

1万円寄付コース
・お礼のメール
・活動報告書
- 申込数
- 44
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2023年6月

緊急支援|被災重なるフィリピン、台風25号被害へのご支援を
- 現在
- 565,000円
- 寄付者
- 63人
- 残り
- 37日

ひとつの心室で生きていく。フォンタン手術の患者をみんなで支援したい
- 現在
- 3,409,000円
- 寄付者
- 171人
- 残り
- 30日
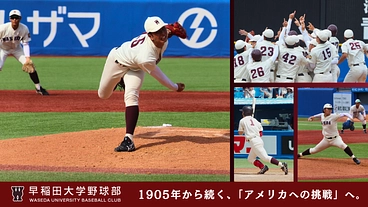
早稲田大学野球部 世界へ!アメリカ名門大学と究める文武両道への挑戦
- 現在
- 11,792,000円
- 寄付者
- 330人
- 残り
- 19日

食料支援を行うフードバンクを支えたい|マンスリーサポーター募集中!
- 総計
- 62人

JWCサポーター大募集中!傷付いた野生動物を救いたい
- 総計
- 253人

野生に帰れない猛禽類のために|猛禽類医学研究所マンスリーサポーター
- 総計
- 524人

野良猫問題を根本から解決したい!不妊去勢手術支援の取り組み
- 総計
- 168人

埼玉おもちゃ美術館幼稚園|地域全体で「子育て支援の場」をつくりたい
- 支援総額
- 8,115,000円
- 支援者
- 114人
- 終了日
- 6/30
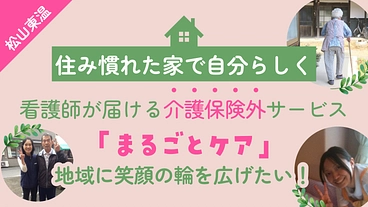
【松山・東温】住み慣れた家で自分らしく!看護師が届ける介護保険外サ
- 支援総額
- 801,000円
- 支援者
- 62人
- 終了日
- 9/5
日本への避難を希望するウクライナの方々を 1人でも多く受け入れたい
- 支援総額
- 6,188,000円
- 支援者
- 144人
- 終了日
- 12/24
ドイツ爪の専門書を日本語で限定出版
- 支援総額
- 5,870,000円
- 支援者
- 229人
- 終了日
- 8/8

プロ野球OB選手が被災地や施設の夢を持つ子どもたちの架け橋に
- 支援総額
- 731,000円
- 支援者
- 76人
- 終了日
- 4/26