
頑張ってください!
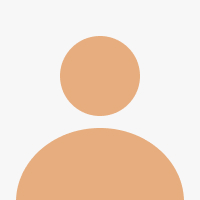






札幌市子どもの権利条例市民会議(略称 こどけん)は、子どもの権利条例制定に向けての活動だけではなく、『札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例』(札幌市子どもの権利条例)成立後も継続して活動し、札幌市の子ども施策についてのチェック機能を意識して活動してきました。
今回のこの書籍の発刊が、全国各地で子どもの権利条例制定拡大の動きにつながることを期待しています。
子どもの貧困・子ども食堂・スクールセクハラ・指導死・ブラック校則等々が一時的な流行り言葉となっても、この国の子ども施策の中心に『子どもの権利』がしっかり位置付けられ無い限り、子どもの生きづらさを解決することが難しいように感じます。
自分の子どもが学校に在学している時に、学校の校則や生徒指導・進路指導に興味関心を持っても、自分の子どもが卒業してしまうとなおざりにしてしまった大人の存在がこの国に子どもの権利を定着させて来なかった遠因なのでは無いかと反省しています。
以前投稿した『最初の一歩』に『追歩…』として若干追加しましたが、書籍の発行を楽しみにしています。
2022.1.11
前 札幌市子どもの権利条例市民会議(略称 こどけん)代表 佐々木 一
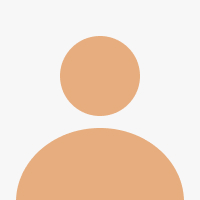




心より感謝し応援しています📣
子ども庁、子ども基本法、救済機関など
子ども施策が充実するきっかけとなりますように!
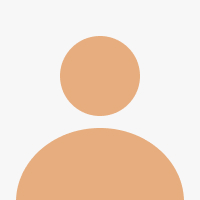

子どもの権利を実現するためにいつも先頭を切って私たちを導いてくださっているネットワークの皆さま、ありがとうございます!
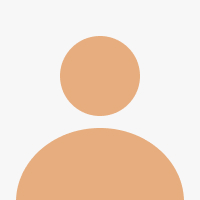
子どもの権利を核に、さまざまな場所でさまざまな営みがどう始まったのかを学び、今後に活かすのはとても重要なことだと思います。成立して、多くの人に届きますように!

早大助手時代はお世話になりました。新たなプロジェクトが進んでいるようで素晴らしいですね。宮崎にお越しの際はお声掛けください。

もっともっと、子どもの権利が当たり前の社会になるよう、微力ですが私もできる限り動いていこうと思っています。


子どもの権利条約を守らない児童相所をジャッジするための、
子どもの権利条約遵守度ランキンAI化してください。
すべての児童相談所こそ、評価されるべきです。












「子どもの権利条約」が多くのおとなたちに広がることを願って、福岡の地からプロジェクトの成功をお祈りしています。出版楽しみです!






私が、子供の権利条約や児童憲章、ユネスコの採択などに出会いましてから24年の時をn経ております。
当時、学校という閉ざされたモンスター化した世俗な無知な保護者から我が子を守りたい一心で探した我が子と私の唯一無二の窓口でした。また出会えて良かったです。






子どもが傷つけられるニュースが流れる度に、胸が痛みます。でも、どうしたら良いのかも分からずにいます。
本当にささやかなではありますが、どこかにいる子が、希望を持てますようにと願い、支援させて頂きます。


オンライン学習会の開催ありがとうございました!応援してます!!!お互い頑張りましょう^_^!

林さんの活動にはいつも感心しています。
本当に民主主義の根幹で有り大切な事だと思っていますので、僅かながらではありますが支援をさせて頂きます。
引き続き頑張って下さい!
松戸で、山崎くんとともに、模擬選挙の活動をしていました、渡辺周一と申します。現在は、障害のある、子ども、若者の居場所事業をやっております。
子ども、若者、障害者等、社会的弱者の権利擁護について、今後も勉強していきたいと思っています。これからも、ご教授下さい。よろしくお願いします。

1997年、当時小学4年の
長男の学級崩壊の時に
相談窓口を探して新宿区
落合の保護者の会(名称は忘れました)に参加させて頂き
埼玉大学の林量俶先生からお話をお聴きして、子供の権利条約、ユネスコの採択を教えて頂きとても参考になり、
親の役割と育て方の観念を変えることができました。



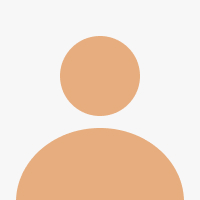
日本で子どもの権利の普及のために活動してくださって本当にありがとうございます。たくさん学ばせていただいています。これからも一緒に頑張っていきましょう!


子どもの権利普及と推進に向けたこれまでのご尽力に感謝します。私の住むまちでも草の根の子どもの権利普及、条例づくりのプロジェクトをスタートしました。NCRCからの発信に学び、勇気づけられています。出版を楽しみにしています。






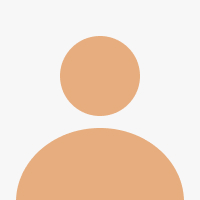
執筆陣が豪華でとても楽しみにしています。
子どもたちが、のびのびと生きられる社会になりますように!
学ばせていただきます。


この条約が広まり、当たり前の世の中になったなら、きっと子どもが育つ環境はずっと良くなっていくことと思っています。



応援しています。多くの人が手に取ってくださる本となりますように!



子どもたち自身が子どもたちの未来、そして今現在のあり方を考え…子どもたち自身がもっと主体的に参加できるような社会へと現状改善していくための一助となる、素晴らしいアクションだと思っています。
応援しています!




