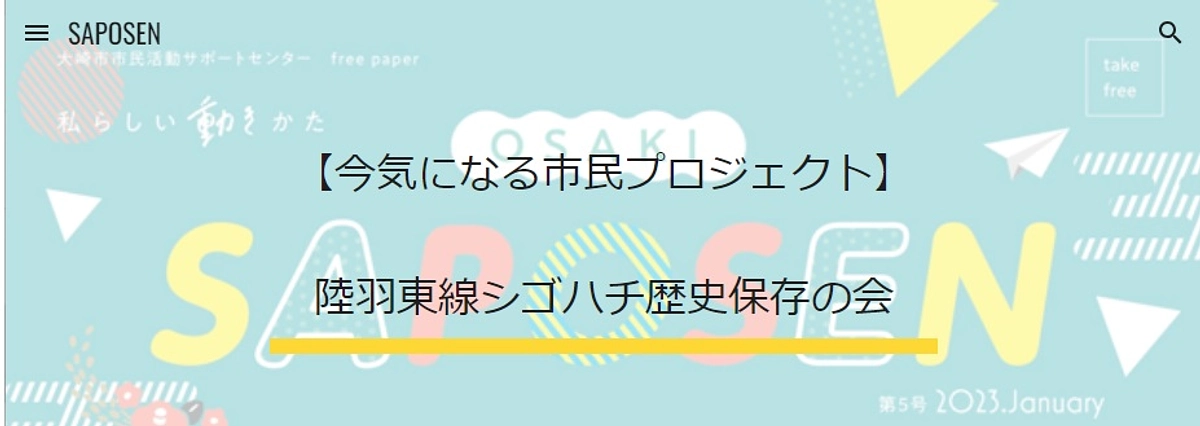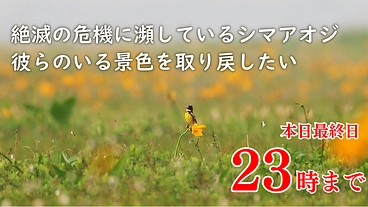支援総額
目標金額 3,000,000円
- 支援者
- 286人
- 募集終了日
- 2024年5月31日
【SLとわたし】#04 元鉄道学芸員
鉄道文化連結会の大場です。
いつも当プロジェクトを御応援いただきありがとうございます!
4月19日現在で約1,800,000円、目標の60%という状況まで来れました!
改めて保存会一同より心から感謝申し上げます!
「SLとわたし」というテーマで行っている活動報告ですが、第4回目は学芸員資格を持ち、鉄道資料館で学芸員経験もある保存会メンバーからのコメントをご紹介させて頂きます。
【SLとわたし】#04 元学芸員

「0」から「1」へ「1」からその先の未来へ
0
初めてみた「シゴハチ」は、今は亡き西古川の19号でした。私の家は19号があった児童遊園に近く、家もまた陸羽東線の線路のそばの立地、自然と鉄道に惹かれていきました。
幼稚園ごろまでは午前3時15分ごろ、家の脇を通過する寝台特急「あけぼの」の迂回運転を見るためわざわざ起こしてもらって見たりするほどでした。
小学校のころ、親が「鉄道」だからと録画していたのが思いっきりテレビの『今日は何の日』の鉄道開業の話でした。それから何本かその番組での鉄道特集を見ていくうちに「鉄道の歴史」に持つようになりました。ちょうどよくNHKで『プロジェクトX』や『その時歴史が動いた』が放送されており、見ていくうちに鉄道の歴史だけでなく、歴史全体に興味を持つようになっておりました。
当時、シミュレーターで早々に運転士の夢を挫折していたため、歴史関係の仕事が出来たら良いなぁと漠然と考えていたように記憶しています。鉄道資料館の非常勤でも採用されることになろうとは夢にも思わなかったでしょう。
話が脱線してしまいましたが、今回原稿を書くにあたり、一応「学芸員」の資格を持っていますので文化財的な話を少々書いてみようかと思います。
1
さて「文化財」という言葉を聞いた時、皆さんはどんなものを連想するでしょうか。
奈良の法隆寺、兵庫の姫路城、富岡製糸場、高輪築堤等々、その答えは人により多様化と思われます。
こうした数多ある「文化財」ではあるが、新しいノートルダム寺院の火災などの事例から見てわかるように、文化財は1 度失われたら、決して元に戻すことはできないものであります。
これは「文化財」を扱う上での基本的な考え方です。
一方、保存車両を含めた「近代のモノ」の多くは必ずしもその様には見られていないのが実情です。
保存車両を「老朽化したから、危ないから」という理由で解体されてしまっているというこの事実・現実が、何よりの証拠です。
現在、各地で保存車両の劣化が課題となっています。保存車両を「残す」か「壊すか」の選択に今にも迫られうる車両が多くあるのが現状です。
2
現在、公園などに展示されている保存車両はあくまで公園の「遊具」という扱いに過ぎません。
たしかに遊具としてみたならば老朽化しての撤去は致し方無いといえます。
しかし、果たして保存車両=遊具でよいのかはまた別の問題です。
1872 年に新橋から始まった鉄道は、以後の日本の歴史に大きな役割を担ってきました。鉄道なくして、近代化の歴史を語ることは不可能です。
鉄道は町と町の時間的距離を格段に縮めただけではなく、各地域に「新しい文化」をそ
れまでとは比べ物にならない速さで各地に伝えました。イギリスの鉄道作家、ウォルマーが『世界鉄道史』の中で述べているように、鉄道により「変わらなかった」ことを探
すほうが困難と言えます。
そうした変化が果たしてそれが良かったのかは別として、こうした鉄道が担った役割は
決して小さいものでありません。
鉄道によって我々は「何を得て」、「何失ったのか」、といったことを考えるうえで鉄道車両は、それを考える材料と十分になりえるのです。
確かに「近代」という言う時代は、歴史とみるにはあまりに時代が「今」に近すぎるの
かもしれません。
近すぎるがために、「文化財」と見られないという側面は確かにあります。
しかし、教科書にある今からは遥か昔の「中世」や「近世」にも、我々が今、「現代」と呼ぶ時間がそれぞれの「その時」に確かにあったことを忘れてはいけないことだと思います。
つまり、今我々が博物館だったり観光地だったりで「中世」や「近世」のものをみているように、数百年後、同じような視点で、「昭和・平成」のものを見るが来るということです。
その時に「明治~昭和」の人々はどう生きたのか、「明治~昭和」とは一体何だったのか、を伝えうる「モノ」を、「文化財」として、同時に歴史を物語る証人として、後世へ残し、伝えていく必要があると思います。
そして
それができるのは「今」を生きる我々だけです。
3
さて「同じ形の蒸気機関車はあちらこちらにある」いう指摘があります。
保存車両を解体の理由を説明する時、や解体のニュースへのコメントなどによくあがるこの指摘、はたして、必ずや正しいのでありましょうか?
確かに設計図をもとに作られていますから、機関車の見た目はどれも殆ど同じで指摘は的を射ているようにも見えます
しかし、この指摘には大きな視点が抜けているようにも思えるのです。
そして、その視点こそ、なぜ機関車を「残すのか」という理由にもつながる点だと思うのです。
それは「モノ」が持っている背景、「歴史」です。
モノにはそれぞれのモノが歩んだ固有の歴史があり、それらはモノにしかない背景を背負っています。
地元を走った保存車両であれば、それはなおのことで、地元を走った車両は、ほかの機関車でもない、その機関車自身に他なりません。
例えば岩出山のC58-114であれば、大崎地域にどんなモノを運び、人を動かしたのか、そして周辺地域をどう変えたのかといった、近代における大崎地方の「地域の歴史」という大きな視点の歴史をも語りうるということであります。
その価値や意味は、ほかの地域の同種の機関車ではとってかわりようのない。その地域の近代を支えたモノとして重要な意味を持っているのです。
ゆえに、決して 1 両として「同じ機関車」 ではなく、もっと言えってしまえば「歴史を持たない車両は1両もない」のです。
ことに地域を走り、地域で保存された機関車は、それ自体が地域の歴史を語る貴重な史料となる可能性を秘めています。
4
たしかに、多くの自治体の保存車両は、導入時はあくまで単なる「モニュメント」のような存在であったかもしれません。しかし、先述のとおり保存車両のその背後にはおのおのの車両にしか決して持ちえない、「地域の歴史」があります。
保存車両には、それらが走り運んだ「昭和」という時代を示す貴重な資料としての文化
財的な価値や意味がある。したがって保存車両を残すことは、「地域の昭和という時代」の歴史を後世に残していくということにもなるのです。これはほかに数多ある同型の車両で
は決してできないことです。
岩出山のC58は、陸羽東線とその沿線の歴史を物語る貴重な史料になりえます。
当初大崎市のC58は3両すべてが解体となり文字通り「0」になるはずでありました。しかし、保存運動の結果、うち1両を保存へと転身することができ、「0」を「1」にすることが出来ました。
これからこの大切な「1」を、これから先の未来へとつなげていくために、C58を修復し、整備中の岩出山駅鉄道資料館も含め「地域の宝」として後世に残して行きたいと思っています。
CFへのご支援をよろしくお願いいたします。
リターン
3,000円+システム利用料

【メール返礼】全力応援C58!
会より御礼状(メール)をお送りさせていただきます。
(郵送リターンなし)
- 申込数
- 56
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2024年6月
5,000円+システム利用料

【メール返礼】ファイトC58!
会より御礼状(メール)をお送りさせていただきます。
(郵送リターンなし)
- 申込数
- 20
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2024年6月
3,000円+システム利用料

【メール返礼】全力応援C58!
会より御礼状(メール)をお送りさせていただきます。
(郵送リターンなし)
- 申込数
- 56
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2024年6月
5,000円+システム利用料

【メール返礼】ファイトC58!
会より御礼状(メール)をお送りさせていただきます。
(郵送リターンなし)
- 申込数
- 20
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2024年6月

清瀬市から未来へ— 幻のロマン客車「夢空間」の鼓動を、再び。
- 現在
- 2,316,064円
- 支援者
- 113人
- 残り
- 10日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ
#ものづくり
- 現在
- 217,476,000円
- 支援者
- 12,357人
- 残り
- 29日

百寿の琴電23号、次世代に受け継ぐ応援を!
- 現在
- 424,500円
- 支援者
- 44人
- 残り
- 9日

「網走鉄道」 レール延伸 ホーム設置 運転設備拡充工事のご支援願い
- 現在
- 562,000円
- 支援者
- 32人
- 残り
- 25日

上毛電気鉄道|次の100年を共につくる、新たな”なかま”を迎えたい
- 現在
- 3,581,000円
- 支援者
- 125人
- 残り
- 22日

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける
- 総計
- 679人

“鉄道を撮る、鉄道に乗る”を楽しむ活動で鉄道会社を応援したい!
- 総計
- 43人
眼球摘出手術を受けさせてあげたい!
- 支援総額
- 404,000円
- 支援者
- 134人
- 終了日
- 4/10

発達障害児の子育も楽しめる。必要な人や情報とつながるカフェを
- 支援総額
- 1,900,000円
- 支援者
- 123人
- 終了日
- 6/29
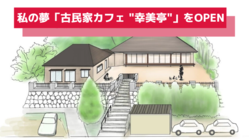
古民家を再生して、私の夢がすべて詰まったカフェを作りたい!
- 支援総額
- 776,000円
- 支援者
- 76人
- 終了日
- 3/19
秋田を美しい高齢女性の活躍する町へ
- 支援総額
- 150,000円
- 支援者
- 19人
- 終了日
- 10/31
兵庫「たつの昆虫館 」の心でつなぐ昆虫館応援プロジェクト
- 支援総額
- 171,000円
- 支援者
- 27人
- 終了日
- 5/31