
寄付総額
目標金額 15,000,000円
- 寄付者
- 1,861人
- 募集終了日
- 2017年9月8日
小児がんの子どもの成長・発達を支える医療保育(保育士)
小児入院病棟の保育士、というと、「小児医療施設には保育士もいるんだ」という事実自体が驚きだったのをおぼえています。医療保育とは、どういったお仕事なのでしょうか。

日常的に、他職種よりも患者さん、家族に近い立場で接することができるスタッフだと思います。病棟配属なので、医師・看護師の次に一番良く知っていて、医療的な部分の情報を得る、プラス、こちらからも患者さんや家族の情報を提供するといった情報共有をしています。
主に成長・発達の援助をしているので、どの発達段階にあるのか、どの辺りに遅れがあるのか、もうちょっと援助してもらった方が良いのかなどの情報共有が中心です。ご家族とお話しすることも多いので、家族支援ということでは疲労が溜まってきたりストレスが出てきたりという御状況に合わせてご家族の心理的サポートの必要性について情報共有して、どの職種がどれだけサポートできるかなどをみんなで考えてもらっています。
年齢層としては、どのような世代が中心ですか?
担当している入院病棟では幼児・未就学児が多いのですが、学童・思春期の多い場所もあります。
どういうケースでどういうパターンがあるか、経験談をお話いただけますか?

たとえば3~4才の小児がんの患者さんで、入院初期はずっとベッド生活が続いていた、ということが有りました。私たちは保育園や幼稚園と同じような環境を提供するために午前中は集団保育を提供するんですけど、ずっと出てこられなくてやっと制限が解除されて安静度がベッド上からプレイルームへと集団参加が可能です、となったときに、ずっとベッド上だと親子の関わりだけとか、他職種とか違う親以外の大人、リハビリ、医師看護師が入ったりするくらいで人為的環境がものすごく限られる状況が有りました。
自宅だったらご家族、そして保育園や幼稚園に行くので他のお友達とも交流していますが、入院って極端に関われる人が限られてしまって。その中でも一ヶ月以上ずっと生活して外に出られるようになったときに、体力も落ちているし、他の子ども達と関わる時間も極端に減っていたのを元の生活に戻していきたいとなったときに、もともとリハビリとかいろんなケアが入っていたところを「集団活動に参加できる」という目標を立てました。
すると、リハビリの時間をずらしてもらうとか、あえて集団保育の時間に参加するために看護師にも入浴とか清潔ケアの時間をずらしてもらうとか、医師にも治療の時間をずらしてもらうとか…いろんな職種にお願いをして、その子がもともと入院前に送っていたであろう幼稚園・保育園に通っていたような環境に参加するために、保育士やご家族、他の患者さんらなど様々な人の関わり方の中で遊ぶということを実践しています。
保育といっても、目標・課題は世代や発達段階によって全く異なるのだと思います。「こうなったら良いな」と目指していることは、どういったことですか?
私は未就学児が多いので、たとえ病気はあっても“その子らしさ”を無くさずに入院生活をおくれると良いなぁ、と思っています。
幼い時期のこどもは人間の基礎となる部分というか、人格ができあがる部分というか、これから成長していく上で一番重要な部分、いろんなものが確立されるところにいるので、病気のことも含めて一番重要な時期に関わらせていただいているという実感があります。だからこそ、病院という特殊な環境下であっても、子どもにとって重要な「遊び」というのがゼロにならないように関わりたいです。
意外と、ご家族やご知人・ご友人らは「入院を機に人が変わった」という感想を持たれることがあります。それは、落ち着いていたり、攻撃的になる子もいます。そんな時、「環境って大きなものなんだな」と思い知らされます。
どうしても、普段の生活以上に大人の中に囲まれます。しかも、囲まれても親戚ではなく見知らぬ人ですし、嫌なことも痛いこともされるし――というところで、少しずつ彼らが経験したことによって、どんどん人が変わっていってしまうんだろうな、と思います。
自分の思い通りにいかないことの多い現状で、それらを減らすために「何ができるか」「成長過程にいるこどもに関わるのだから、よく考えてやらないと難しいな」と、すごく思います。幼少期、学童期、思春期の中で、人はいろんな計り知れないものを経験しています。ここでの経験を、どこまで覚えているかは個々それぞれですが、2~3才児の子は覚えている子は覚えていますし、今後の人生少なからず影響はするだろうと思います。
保育士だけでなく、リハビリ、臨床心理士・精神科医、CLSといったいろんな方々と情報共有することが重要です。PSC(心理社会的ケア)カンファレンスでは、より心理的支援をおくる職種でカンファレンスをやるので、それぞれの職種からいろんな関わり方の話を聞いて保育士は病棟でどういった関わり方ができるか、こちらからこういうときはどうするべきか、というところを相談します。情報共有と相談、実践を繰り返す毎日です。
普段の入院病棟の様子はどうですか?

病院保育は静かに遊んでいるだけじゃないんです。全然静かではないんですね。
学童期のこどもの多い入院病棟を担当しているので、毎週水曜日にそよ風分教室に行っていて普段あまり密に関わることができていない時期もあります。それでも、水曜日は早く帰ってくるので、製作をやったりとか、「さぁみんなで作るよ!」という感じではなくて作って遊べるものを取り組んだりとか。
この間は、ビュンビュンゴマを一緒に作って皆すっごい笑顔になってくれて。その日の朝から私がやりながら患者さんのところに挨拶に行って「これ作るよー」って言って、食いついてくれて「お母さんにねだって厚紙買ってきてもらった」とか。ブームになってしまった(笑)。
男の子達がビュンビュンゴマを持っているのを見て、工作が好きな女の子に「なんで私にはくれないの?」って言われて。次の週に女の子はやった。それでみんな満足して、みんなビュンビュンしてビュンビュンが流行ったことがありました(笑)。
年齢によって反応は違いますか?
中学生の子もいて、たまたまみんな男の子だったので模様もこだわって「こういうふうな顔もするんだな」って分かったり、あとでお母さんから「この子はこういうことが好きだったので遊んでくれてよかったです」とおっしゃっていただきました。作った後に自分の持っているペンで活動以外の時間でさらにパワーアップして「こういう色合いになったよ」って教えてくれたり(笑)
学校に通っている子たちは、学童と治療の両方を頑張らないといけないので、学校の勉強に遅れるとか、友達の輪に戻れないかもしれないという不安もすごく強いです。治療中不安にかられるというのは、結構すごいストレスになるので、そういうところでストレス発散、気分転換する時間を設けないと、と思っています。
これまでご経験してきた中で、想い出にのこるケースはありますか?
幼児の1~2才ぐらいの終末期に入る子で、治療も全てできなくてご家族がお家に帰らないという選択をされて最期は病院で過ごすというときになって、それでもその子と保育士との関係はあって、遊ぶのはどんなに苦しくても好き、どんなときでもどんなに呼吸が苦しくても私が来れば遊ぶ――という子がいました。
お母さんも、御本人が具合悪いから家にも帰れずずっと泊まっていて、そんな中でも心配だけど疲労感はすごく溜まっていて。お母さんもいろんな治療とかは嫌がったりするけど、遊ぶのは(保育士が)来てくれると表情が変わるし、できる限り遊んでほしいという想いもあって。
そのときの受け持ちの看護師さんと相談して、お母さんも疲労感が溜まっているし、本人も子どもから離れられないし、保育士がいるときは本人は嫌だって言わないし、保育士がいるときがお母さんが離れられる唯一のチャンスかもということもあって話し合いを進めて、遊んでいるときはお母さんに休憩に行ってもらう・本人はギリギリまで遊んでもらう――という計画をして、亡くなる前日まで毎日遊んでお母さんにも休憩してもらう、ということを続けました。
最後の方は起きるのもできなくて、遊ぶってワーイって活発に遊ぶだけではないので、一緒にDVD観るとか、絵本を静かに見るというのも(本人が遊びだと思えば遊びなので)遊びは遊びで。それを、ギリギリまで続けられました。
お母さんも亡くなった後にお会いして、お父さんと振り返ったときに「ギリギリまで遊べたというのはいい環境だったな」と言っていただいたことをおぼえています。スタッフとも、お母さんも休憩に行きたいけど行けないという状況であったし、本人も遊ばせたい、いろんな想いがあって…「最終的には遊ばせることができたし、自分も休憩に行きながら本人に最期まで付き添うことができた」というお話を聞けたのが、印象にのこっています。
何か、目指すところを果たせたという瞬間はどのようなものなんでしょうか?

きちんと情報共有していけば、それぞれの方が専門家なので、自分たちの領域外を聞いてそれを次のときに実践してみて良い方向に向かうことが有ります。
治療は「完治した」ということがゴールですが、保育は成長・発達をテーマにしているお仕事の時点で、人生そのものというか、終わりがないお仕事なんですね。
「医療は土台なんだけど、上にあるのは生活だから、ここ(生活)を何とか良くしよう」という見方をしていないと“医療ありき”という逆の枠組みになりがちです。
こどもにとっては、ここが生活の場所ですし、長期入院になればなるほど家以上にここで過ごしている人もいるわけです。入院には、いつかは終わりがある。そこで「こういうことができたね」という振り返りを表現できるということ、退院するまでの期間をより良くできることが大切なんだと思います。
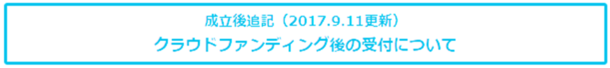
クラウドファンディグでのプロジェクト期間は終了いたしましたが、まだまだご理解・ご支援の輪の広がりを感じております。そして、一人でも多くの方々の願いのとどく企画にできればと思っております。 小児がんと戦うみんなの願いである「無菌室」の新設に、引き続き力をお貸しください。
▼お申し込みはこちら ※今年度中、もしくは資金調達の目途が立ち次第、募集は終了致します
今後とも、国立成育医療研究センターを何卒よろしくお願いいたします。
○こんな記事も読まれています
ギフト
3,000円

小児がんの子どもの願いを一緒に
■小児がんセンターサポーターに任命:皆さまにはサンクスメールと無菌室(クリーンルーム)稼働の報告メールをお送りします
■御礼状・ 寄附金品領収証明書の送付
- 申込数
- 1,104
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2018年2月
10,000円

小児がんの子どもの願いを一緒に
■小児がんセンターサポーターに任命:皆さまにはサンクスメールと無菌室(クリーンルーム)稼働の報告メールをお送りします
■御礼状・ 寄附金品領収証明書の送付
- 申込数
- 557
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2018年2月
3,000円

小児がんの子どもの願いを一緒に
■小児がんセンターサポーターに任命:皆さまにはサンクスメールと無菌室(クリーンルーム)稼働の報告メールをお送りします
■御礼状・ 寄附金品領収証明書の送付
- 申込数
- 1,104
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2018年2月
10,000円

小児がんの子どもの願いを一緒に
■小児がんセンターサポーターに任命:皆さまにはサンクスメールと無菌室(クリーンルーム)稼働の報告メールをお送りします
■御礼状・ 寄附金品領収証明書の送付
- 申込数
- 557
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2018年2月

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ
#ものづくり
- 現在
- 217,719,000円
- 支援者
- 12,379人
- 残り
- 29日

1頭1頭と向き合い続けるために。引退馬たちに安心安全な新厩舎建設へ
- 現在
- 73,949,000円
- 支援者
- 6,389人
- 残り
- 32日

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける
- 総計
- 679人

入院する子どもたちを笑顔に!ファシリティドッグ育成基金2025
#子ども・教育
- 現在
- 6,991,000円
- 支援者
- 559人
- 残り
- 25日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ
#伝統文化
- 現在
- 61,785,000円
- 寄付者
- 2,862人
- 残り
- 29日

「合う肌着がない」難病の娘に笑顔を!家族で開発、超細身キッズ肌着
- 現在
- 1,545,000円
- 支援者
- 231人
- 残り
- 18日

ひとつの心室で生きていく。フォンタン手術の患者をみんなで支援したい
- 現在
- 3,435,000円
- 寄付者
- 174人
- 残り
- 29日







