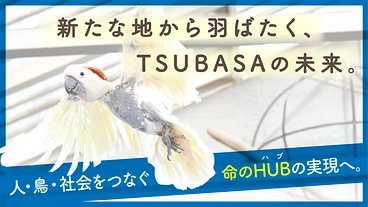支援総額
目標金額 1,200,000円
- 支援者
- 111人
- 募集終了日
- 2020年1月24日
#応援「子どもの居場所としてのプレイバスの重要性と4つの課題」
大学生のとき、東日本大震災をきっかけに知り合った「善さん」こと早川大さん。
仲間たちと立ち上げた防災サークルのメンバーに指導もして頂き、
その時は、とても防災支援や対策に精通している方だと思っていたのですが、
なんとプレーワーカーとしても活動していて、こども×あそび×防災と、
時には行政へもアドバイスや研修へ赴く専門的でエネルギッシュにご活躍されている善さんからとても熱い、応援投稿を頂きました。
20歳からの僕の紆余曲折・遍歴を間近で見てくれている方だからこその
メッセージだと思います。ありがたい。。
ぜひご一読をお願いいたします!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
子どもの居場所としてのプレイバスの重要性と4つの課題
危機管理アドバイザー
プレイワーカー(ワーカー歴17年)
株式会社kipuka代表
災害支援団体bousaring代表
早川 大
増田さん、いや団長と呼ぼう。
「”あそび”を出前するプレイバスをみんなでつくりたい!」
そんな言葉を聞いた時はとても嬉しく思いました。
団長と初めて会った時、彼はまだ学生でした。
夢だけで生きているのかと思っていましたが、いやいや、とても堅実で
社会を見据えた考えを持っていました。
彼は卒業後も着実に夢に向かっていました。
その彼が選んだ「遊び」の世界。
これは子どもと寄り添う特異な業務です。
ワークショップや本では学びきれないのが「遊び」の世界です。
遊びに関わる人はみんなが知っている言葉があります。
それは「技術」です。
「技」は本やワークショップで学びます。
そして「技術」は個人の個性・感性・経験です。
自分で学びとっていく部分です。
いろんな場面でたくさんの経験をすることにより、成長していくことができます。
子どもの世界に入ると子どもと正面で向き合います。

今現在、子どもの世界では課題がいくつかあります。
空間・時間・仲間そして隙間です。
「空間」は子どもの遊び場所が減少していることが挙げられます。
各地方に行くと田畑や山、森や川などがあり地元の方は「この地区全体があそび場です」とおっしゃいますが、よくよく聞くと......
田畑は個人所有の土地だから遊べない。
川は流されたら危ないから遊べない。
森や山はカラスがでるから入ってはいけない。
じゃあどこで遊んでいるのか聞くと家の中が大半だと聞きます。
これは東日本大震災の時に東北で知ったことでした。
講演で西の方に行っても同じ状況でした。
「時間」は以前、身内の子のタイムスケジュールを決める手伝いをしたことがあります。
完成したそれは、ブラック企業と同じようなタイムスケジュールでした。
タスクが達成できない場合は睡眠時間を削るか休日を削って対応するとのことです。これはあそび場に来る子どもも同じだと教えてくれました。
「仲間」は核家族化が進み共働きの家庭も多い今、多くの小学生が学童保育などに行っています。また、塾や習いごとをしている子どもがいる一方で、
学童にも行っていない、習いごともやっていない子どももいます。
放課後、友だちと遊びたくても遊ぶ仲間がいない子どももいます。塾や習いごとのタスクが多い子のほとんどは、学校の子とは遊ぶことが少ないと聞きます。クラスでは自分が出せないとのこと。
これを深掘りすると、”外”の自分で作った「理想の自分」が丁度と話しました。
どうも外の友だちは、趣味で繋がるので本名ではなくSNSネームなどで呼び合い、好きな時に会って、好きな時に帰れる。気兼ねしない関係だそうです。
教えてくれた子いわく、理想の自分でいられる時間のようです。これは、「気が合わない子が実は気が合う」や「いつの間にか仲良くなる」「名前なんか知らないけど一緒に遊んでいた」というような友だちづくりに必要な経験ができていない環境になってしまいます。
だからでしょうか「知り合いは必要だけど友だちはいらない」と言っていました。
そして、今のあそびの世界に足りていないのが「隙間」です。
これは静岡のあそび場「たごっこパーク」を運営している渡部達也さんから学んだ言葉です。この言葉がとても重要だと考えます。
いまの町や村、地域に「隙間」がない。
それは何故か?
昔は子どもだった大人が「隙間」を削るように規則を作り、
「危ない」という魔法の言葉で、
遊びにいく場所をつくっているからです。
だからこそ今の社会には「隙間」であるあそび場が重要になります。
子どもたちのあそびには逃げ道である「隙間」が大切です。
某地域の公園は、のきなみボールを使った遊びができなくなり、声をあげて遊んではいけないという規則があります。
子どもが声を上げると警察官が来て注意を促されます。
親は子どもに声を出さないで遊ぶように「子どもに伝える」を通り越して「子どもを躾ける」という状況。
このような環境を変えるにはどうしたらいいか。
それは、規則を増やすのではなく、大人が「あそび」を増やしていくことが大切です。
とはいえ、それには固定の場所を借りるか、身近な場所をあそび場にするという選択肢から始まります。
団長は、プレイバスという手法を使い、身近な場所をあそび場に展開していきます。
「あそび場づくりは地域づくり」でもあります。
地域に子どもを見守る大人がいたら、子どもたちは町を使って遊びを展開できます。
よく大人が言います。「もしかしたらケガをするかもしれない」
でも小さいケガを沢山することで、大きなケガの予防にもなります。
そして、沢山失敗することで、成功への道を見つけます。

かのエジソンも失敗することで学びました。
「失敗は積極的にしていきたい。なぜなら、それは成功と同じくらい貴重だからだ。失敗がなければ、何が最適なのかわからないだろう」。
あそび場で成長した子どもを見る限り、子どもの頃、沢山遊んで失敗してきた子は、大人になって失敗しても立ち直りが早いと感じます。
このような大人が増えれば「規則」を増やすことは必要がなくなると思います。
そして、自分が沢山失敗した経験があるからこそ相手の気持ちに寄り添えます。
「規則」は「怖さ」からやってきます。
想像できないことが怖さを増大させます。
怖さを増大させない為には、失敗も含めた経験が必要です。
それには、子どもを信じて見守ることが大人には必要です。
子どもを信じて見守ること。それが団長にはできます。
彼のように「あそび場」に対して新たな手法で地域をつくる。
プレイバスを使い様々な地域にあそびを広げていく。
とても嬉しい限りです。
これから、団長はプレーワーカーを名乗ることになります。
同業者として期待しかありません。
団長、いやプレイワーカー増田さん!
応援してます!頑張ってください!

リターン
5,000円

この挑戦、乗った!
・団長より心からの感謝メッセージ
※直筆がよい方、別途ご連絡下さい。文字には自信がありませんが、心を込めてお書きします。
- 申込数
- 46
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2020年2月
5,000円

プレイバスDIY優先招待券+お礼のメッセージ
・団長より心からの感謝メッセージ
・プレイバスDIY優先招待券
★プレイバスDIYイベントの際、優先的にご参加いただけます!
- 申込数
- 17
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2020年2月
5,000円

この挑戦、乗った!
・団長より心からの感謝メッセージ
※直筆がよい方、別途ご連絡下さい。文字には自信がありませんが、心を込めてお書きします。
- 申込数
- 46
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2020年2月
5,000円

プレイバスDIY優先招待券+お礼のメッセージ
・団長より心からの感謝メッセージ
・プレイバスDIY優先招待券
★プレイバスDIYイベントの際、優先的にご参加いただけます!
- 申込数
- 17
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2020年2月

貧困・虐待などで親を頼れない若者に伴走支援を|若者おうえん基金
- 現在
- 7,092,000円
- 支援者
- 330人
- 残り
- 7日

上毛電気鉄道|次の100年を共につくる、新たな”なかま”を迎えたい
- 現在
- 3,581,000円
- 支援者
- 125人
- 残り
- 23日
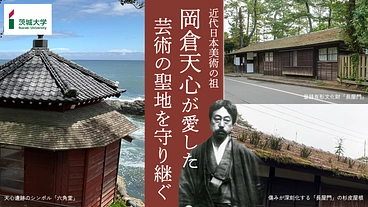
五浦美術文化研究所|雨漏り進む有形文化財・長屋門に一刻も早い修繕を
- 現在
- 2,957,000円
- 寄付者
- 97人
- 残り
- 34日

清瀬市から未来へ— 幻のロマン客車「夢空間」の鼓動を、再び。
- 現在
- 2,316,064円
- 支援者
- 113人
- 残り
- 11日

子どもたちの「心の遊び場」を未来へ 〜座間味小140周年記念事業~
- 現在
- 1,862,000円
- 寄付者
- 105人
- 残り
- 6日

10周年記念事業「東北ゼブラ会議 2026」開催!東北創生の次代へ
- 現在
- 940,000円
- 支援者
- 33人
- 残り
- 32日
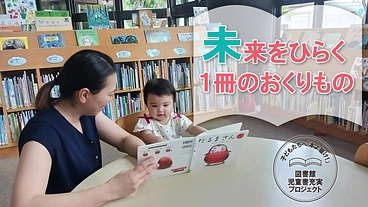
子どもたちへ「本よ届け!」〜図書館 児童書充実プロジェクト〜
- 現在
- 802,000円
- 寄付者
- 72人
- 残り
- 11日

沿線周辺住民の固い絆で開業した地域の誇り|三蟠鉄道の記録集発刊
- 支援総額
- 2,514,000円
- 支援者
- 213人
- 終了日
- 10/29

廃校の危機を乗り越えた、城山西小学校と孝子桜の奇跡を映画に!
- 支援総額
- 2,561,000円
- 支援者
- 162人
- 終了日
- 6/29

他社より20%安いロレックス時計店を中野に出店したい!
- 支援総額
- 0円
- 支援者
- 0人
- 終了日
- 5/5
田舎町にも人々が気軽に集まれる憩いの場を!
- 支援総額
- 255,000円
- 支援者
- 26人
- 終了日
- 5/17

「第21回鏡川緑地公園イベントin紅葉橋」で花火を打ち上げたい!!
- 支援総額
- 317,000円
- 支援者
- 29人
- 終了日
- 10/31