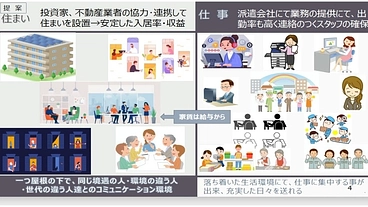支援総額
目標金額 350,000円
- 支援者
- 38人
- 募集終了日
- 2014年9月26日
【カカオの発酵について Vol.3 】
日本の皆様こんにちは。
ガーナより、代表の野呂です。
前回はカカオの発酵を二段階に分けたうちの第一段階「アルコール発酵」について記事にいたしました。
今回はその次の段階である「乳酸発酵」「酢酸発酵」について触れてみたいと思います。
アルコール発酵では、カカオの温度を40℃以上にまで上昇させ、酵母によってパルプが分解されアルコールが生成されるのと同時に、豆と豆の間に空気が通るようになることをお伝えしました。
そうなるとカカオ豆全体は酸素が入ってくる「好気状態」になります。
状態が変わるので活動する菌類も変わってきます。
ここで活動するのは「乳酸菌」と「酢酸菌」です。
彼らは好気状態で活発に働き、カカオ豆に様々な影響をもたらします。
またこの段階で人の手による撹拌を行います。撹拌の有無、頻度は地域によって異なります。
ガーナでも撹拌をするところとしないところがあるみたいです。
今回は乳酸発酵に移った段階で一日に一度撹拌を行いました。
乳酸菌や酢酸菌は酸素を好むので撹拌することによって発酵を促すことになります。

①撹拌によって発酵を促すことで温度はどんどん上昇し、50℃まで近づきます。

さらに、
②アルコール発酵によって生成されたエタノールが酢酸菌によって酢酸に変えられ、この酢酸が豆にしみこむことで、豆の中の細胞組織を壊します。酸素が多くなると酵母はエタノールを生成する能力を失い、アルコール発酵は終わります。
①と②の作用により、カカオの発酵の目的である、
・発芽能力を失わせる。
→もし豆が発芽してしまうと、苗の成長のためにカカオバター(脂肪分)、タンパク質、アミノ酸などの栄養分を消費してしまいます。
・チョコレートの香味物質の前駆体をつくる。
→香味物質自体は発酵の次の工程「焙炒」によって引き出されますが、乳酸発酵によって豆の細胞組織を破壊し、酢酸が豆にしみこむことでパルプに含まれるタンパク質やアミノ酸がポリフェノールと反応し渋みを減らす役割をしてくれます。
つまり綺麗な発酵ができれば渋みを減らし、酸味を持たせることができるのです。
以上の2つが達成されます。
発酵がここまでくると、ようやく「乾燥」に移ることができます。
ここまででおよそ1週間かけます。
発酵→乾燥のタイミングですが、豆の断面図をチェックするカットテストを行います。

カットテストでは「はじめはポリフェノールにより紫色だった豆の色が発酵の作用によって茶色に近くなっているか」を見て発酵の度合いをチェックします。
また豆の香りはどうか、どんな酸系の香りがするか、も重要です。
あとは豆全体が限界熱(最高温度)に達したか、などです。
美味しいチョコレートができるまでにはこんなにも多くのサイエンスが隠されていて、大変な努力を要します。
次回は乾燥工程について説明いたします。
どうぞお楽しみに*
遠く離れたガーナより
代表 野呂謙友
リターン
3,000円

①活動報告書
②サンクスレター
③ガーナで販売されているチョコレート(今回のプロジェクトで製作するチョコレートとは異なります。)
- 申込数
- 27
- 在庫数
- 制限なし
10,000円

引換券#1に加えて、
①帰国後(10月以降)に開催するカカオ豆からチョコレートを作るワークショップのご招待。
※場所は未定
②制作したチョコレート1枚。
- 申込数
- 16
- 在庫数
- 制限なし
3,000円

①活動報告書
②サンクスレター
③ガーナで販売されているチョコレート(今回のプロジェクトで製作するチョコレートとは異なります。)
- 申込数
- 27
- 在庫数
- 制限なし
10,000円

引換券#1に加えて、
①帰国後(10月以降)に開催するカカオ豆からチョコレートを作るワークショップのご招待。
※場所は未定
②制作したチョコレート1枚。
- 申込数
- 16
- 在庫数
- 制限なし

季節の特産品で「行き場の無い猫達」のための活動費をご支援下さい。
- 現在
- 624,000円
- 支援者
- 45人
- 残り
- 7日

より多くの引退馬の幸せな余生を願う|ヴェルサイユ新厩舎プロジェクト
- 現在
- 33,981,000円
- 支援者
- 1,898人
- 残り
- 36日

鳥サポーター募集中|鳥と人の共生を目指す活動にご支援を!
- 総計
- 38人

ワンラブ助っ人募集中!|ルワンダでずっと義足を作り続けるために!
- 総計
- 87人
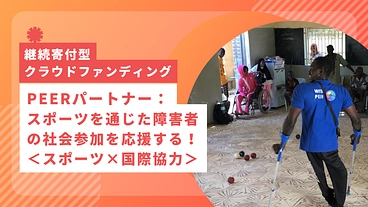
PEERパートナー:スポーツを通じた障害者の社会参加を応援する!
- 総計
- 18人

月1,500円からできる国際協力 10代ママたちに復学機会を!
- 総計
- 22人

世界の女の子が「生理」でも笑顔で暮らせる環境をつくりたい
- 総計
- 30人
宗像海人族を探る。海を護る太古の知恵を国連海洋会議で発信!
- 支援総額
- 490,000円
- 支援者
- 19人
- 終了日
- 12/22
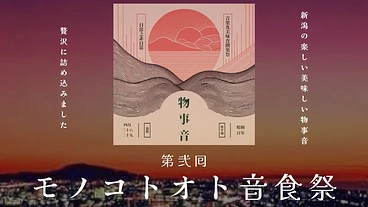
新潟駅前で都市型の野外フェスを実現させてください!音で故郷に集ろう
- 支援総額
- 411,000円
- 支援者
- 36人
- 終了日
- 3/31
本の出版を通して多くの方にTNRの重要性を伝えたい
- 支援総額
- 24,000円
- 支援者
- 6人
- 終了日
- 9/25
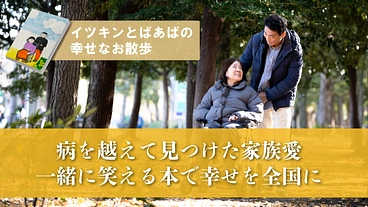
母が書いた児童書で家族愛を伝えたい!読み聞かせと寄贈プロジェクト!
- 支援総額
- 1,924,000円
- 支援者
- 203人
- 終了日
- 4/30
静岡の有名ラーメン屋100店舗を「擬人化した図鑑」を作りたい
- 支援総額
- 15,000円
- 支援者
- 2人
- 終了日
- 4/8