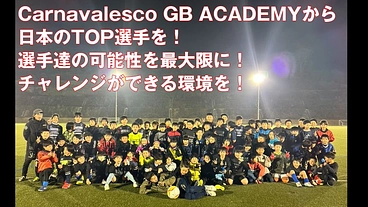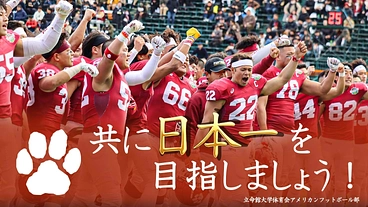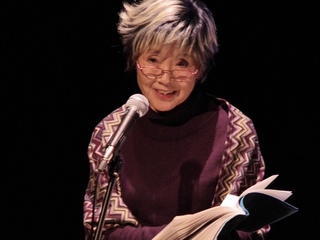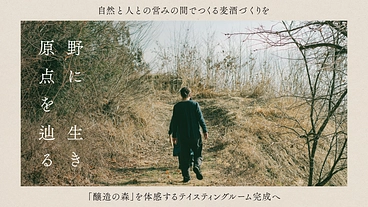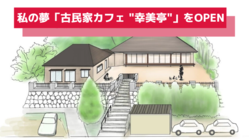プロジェクト終了のご報告
【プロジェクト終了のご報告】
こんにちは。プロジェクト実行者の松本朋子と申します。
この度は無事にプロジェクトが終了したためご報告をさせて頂きます。
この3か月で得た新たな知識、経験、感じたことの全ての始まりがこのプロジェクトであり、皆様のご支援のお陰で自分の人生に於いてかけがえのないものを得ることが出来ました。ご支援いただいた皆様、そして現地でお世話になった方々へ深く御礼申し上げます。

マインツでの経験を通じてチームを経営していくことだけでなく、海外でサッカーをすることや海外でサッカーチームを運営していくことについて学び、更にドイツのサッカー文化に存分に触れられたことで、サッカーというスポーツの魅力に再度気付くことが出来た3か月でした。
日本で18年プレーしてきたにも関わらず、そこでは気づけなかったサッカーの奥深さや国民への影響度、そして「サッカーって本当に楽しい」と心から思う瞬間が多々あり、ドイツに来て更にサッカーが大好きになりました。
サッカー大国ドイツにて学び感じたことを自分の糧とし、今後の将来に繋げていけたらと思っています。そして皆様に支えていただいたように、私自身も日本のサッカー界を支えていける立場へと成長出来るよう引き続き努めて参りたいと思います。
この3か月、辛いときも上手くいかないときも支えてくださった皆様の言葉や想いの1つ1つが私の最大の原動力となり、どんな時でも頑張ろうと思い続けることが出来ました。
本当に本当にありがとうございました!
【活動報告】
今回私は創設4年目のFCバサラマインツというドイツ8部リーグに所属するチームにて、主にチームの認知度をドイツ、日本両国で向上させるための広報を担当させていただきました。
<広報としての主な活動>
①SNSの活性化によるフォロワーの増加
Facebook、Twitter、InstagramなどのSNSを通じてチームをより理解してもらうための様々なコンテンツを新たに作成したり、デザインの工夫や英語、ドイツ語、日本語を使いながら少しでも多くの人に届くためにはどうしたらいいかを追求しながら着実にフォロワーを増やしていくことが出来ました。
最近ではどのチームもSNSを活用しているため、対戦相手と協力してお互いにフォローをし合ったりタグ付けし合ったりして試合を盛り上げるという試みも行いました。リーグ終盤の上位決戦では、相手チームに連絡をして事前に試合への意気込み等をインタビューしてSNSに載せるなど、集客や選手のモチベーションアップへと繋がる活動が出来ました。その試合では8部リーグながらも約120人もの観客を集客することが出来ました。

②宣伝活動による観客数の増加
ドイツには多くの歴史ある地元に根付いたチームが存在し、更に1つの地域にいくつものチームがあるため、地元のファンを増やす事は容易いことではありませんでした。チームをアピールしたポスターを制作して街のいたるところに掲示をお願いしに行ったり、チラシを作成して近くの大学へ配りに行ったりと、チームを知ってもらう為に様々な活動を行いました。この活動を機にマインツ大学で仲良くなった友人が試合を応援に来てくれた時はとても嬉しかったです。

また、ポスターを張らせていただいたお店にご飯を食べに行ったり、そのお店とSNSで繋がったりと新たな関係構築を行うことが出来ました。
③試合運営
スタッフとして試合運営を行うこともスタッフとして重要な役割の1つでした。

選手が振り返りに活用できるためのビデオ撮影、SNS用に写真の撮影、物販にてバサラグッズや軽食を販売、SNSにて速報の投稿、更に少しでも多くの方に試合を見てもらいたいという思いからアベマフレッシュで日本に向けて試合の生放送も行っていました。試合後にはハイライト動画、試合の戦評などの投稿も行っていました。8部リーグにおいてここまで試合の詳細を載せているチームは少なく、地元のサッカーメディアに投稿をシェアしていただいたこともありました。

④スポンサー関連
チーム経営に於いて一番大事な要素であるスポンサー関連の仕事にも携わることが出来ました。どのような企業にスポンサーについてもらうべきか、相手とwin-winの関係を作るにはどうすればいいのか、既存のスポンサーの方々とどのように関係を継続させていくべきなのかといった細かい点を考えながら活動を行いました。実際によく食べに行っていたマインツにある日本食屋さんがスポンサーになって下さったり、スポンサーの方に向けてチームの活動報告を行ったり、SNS投稿の際には必ずスポンサーを意識した形で投稿するなど、色々なことを学ぶことが出来たと思います。

⑤メディアへの記事投稿
記者の方に依頼をして取材をしていただいたり、こちらで記事を書いて投稿したりとメディアを通じてチームをアピールするといった活動も行っていました。フットボールチャネルやドイツNo.1サッカー誌のKickerに載せていただくことが出来ました。更に私たちインターン生も取材していただくなど、サッカー面だけでなくチームの運営面についても知ってもらえるきっかけを掴むことが出来ました。更に日本の学生向けメディアであるco-mediaにて大学生という観点を活かしてバサラマインツのインターンについて記事を書かせていただくなど、これまでにない経験をさせていただきました。
⑥チームの基盤作り
出来たばかりのチームでスタッフも入れ替わりが激しい為、次のインターン生に向けてマニュアルを作成したり、バサラのインターンに興味のある学生と連絡を取り合ったり、新たなインターン生獲得のためにバサラでのインターンについての記事を投稿したりと持続性のあるチーム経営の為の活動も行っていました。年内にて私のインターンは終わりましたが、今後もチームが更に進化し続けていってほしいと思っています。
以上、関わらせていただいた仕事やそこから学んだことはここでは書ききれない程ありますが、ざっくりと私の活動や実績を報告させていただきました。なにもないところからのチーム経営は日々何をするべきかを自ら考え、議論し、実行していくという流れの繰り返しで、とても充実した3か月を過ごすことが出来ました。

<その他学んだこと>
バサラのインターンを通じて学んだことは上記のことにだけに留まりません。仕事を通じてドイツのサッカーリーグの仕組み、ドイツのサッカー文化や、ドイツでサッカーをしている選手たちについてなど様々なことを学ぶことが出来ました。
更にオフの時間を活用してブンデスリーガの試合を観たり、11部まであるカテゴリーの中で様々なカテゴリーの試合を見に行きその違いを感じたり、女子のドイツ代表の試合を観たり、女子のブンデスリーガで活躍する選手に話を聞きに行ったり、Mainz05の練習をみたりと、出来るだけ多くの様々なカテゴリーのサッカーに触れることを意識して行動していました。ドイツサッカーに浸り続けた日々はとても充実した毎日で、サッカーをより深く理解する大きなきっかけとなりました。

~ドイツサッカー事情~
私が見たり感じたドイツのサッカー文化について少しシェアさせていただきます。
マインツの街を歩いているとマインツのグッズを身に着けている人やマインツのステッカーが貼ってある車をよく見かけます。ホームゲーム当日には町からバスが出ていて、町中からみんなマフラーやらユニホームやらを身に着け少し僻地にあるグラウンドまで向かっていく様子が見られ、地域に根差したサッカー文化を感じ取ることが出来ます。

週末にお店を覗くとテレビには常にブンデスリーガが放送されていて、知らない人同士でも一緒にチームを応援している様子が見られスタジアムで観戦するのとはまた違う雰囲気でサッカー観戦を楽しむことが出来ます。
更にドイツにはいたるところに人工芝でゴールのあるグラウンドがあり、市が運営しているグラウンドは誰でもいつでも自由に使うことが出来る環境が整っています。日本の土の狭い公園に比べてはるかに良い環境が整っており、幼い時から自然とサッカーが身近な存在になっていて、ドイツにおけるサッカーの文化的地位の高さを感じる場面が多々ありました。
ドイツのチームは下位リーグのチームであっても歴史のあるチームが多く、対戦時には地元のファンが応援に来ている様子を何度も見ました。グラウンドにちょっとしたゲストルームやバーがついているチームが多く、そこにはチームのこれまでの歴史が書かれていた李、過去の写真が貼ってありました。各チームにはスポンサーもいくつかついており、日本の下位リーグでは見られない光景を目にすることが多くありました。


色々と上記に綴りましたが他にもこの3か月でここには書ききれないくらい多くのドイツサッカー文化を学びました
【収支報告】
皆さまからご支援頂いた資金は、全額現地での活動費及び生活費のために使用させて頂きました。誠にありがとうございました。
・インターン活動費10万円
(ポスター制作、チラシ制作、スポンサー用バナー制作、インタビューボード制作、チーム内イベント企画、その他)
・生活費30万円
(家賃、食費、航空券、交通費)
【リターンの発送状況について】
リターンの発想は1月末を予定しております。
しばしお待ちください!
【今後について】
4月から社会人となる私ですが、これからもサッカーやスポーツに関わりながら様々なことに挑戦していきたいと考えています。今回のプロジェクトで得た多くのものを1つのきっかけとして、これからの自分の将来に活かしていきたいと思っております。
ご支援いただいた皆様との繋がりをこれからも大事にして参りたいと思っています。またこの機会に新たに繋がりが出来た皆様とも是非今後共お付き合いさせていただきたいと思っております。まだまだ未熟者の私ですが引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
ご支援ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。
今後共よろしくお願いいたします。
松本朋子