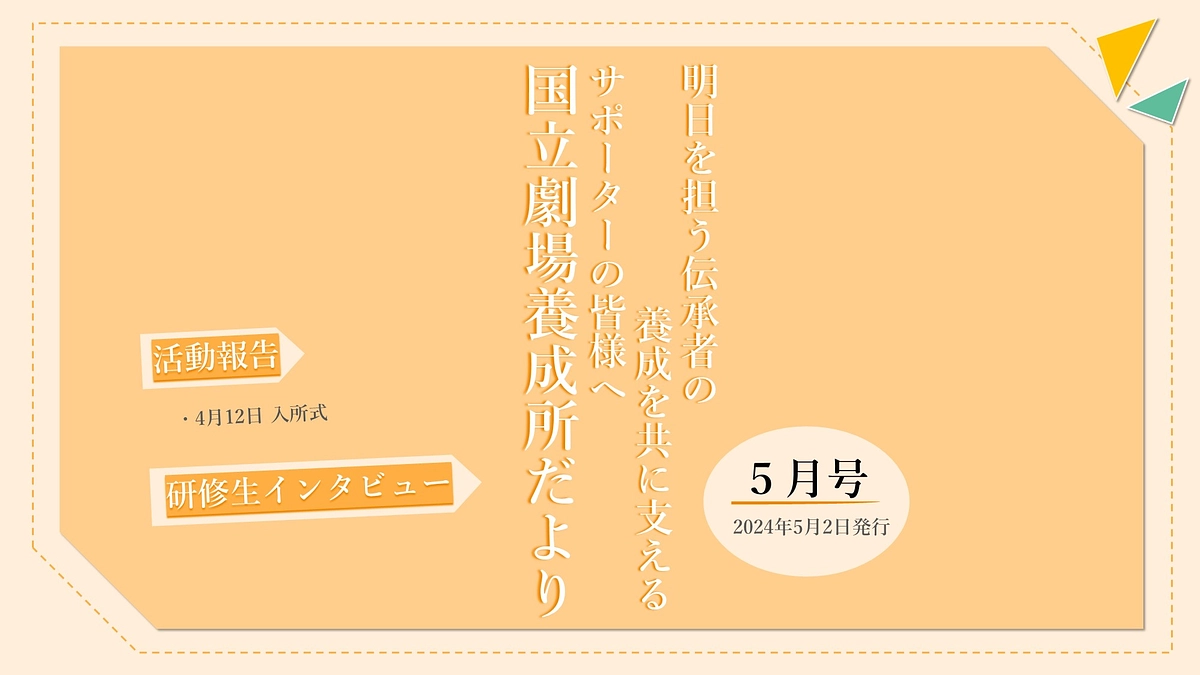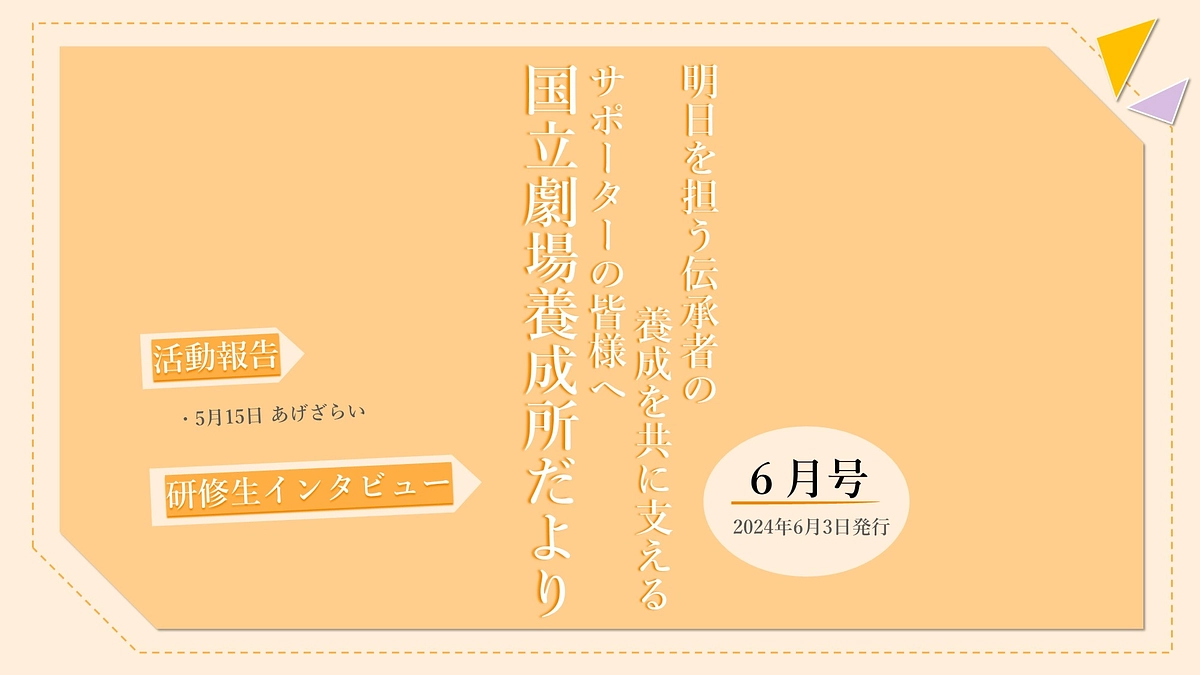このプロジェクトでは継続的な支援を募集しています

マンスリーサポーター総計
【活動のご報告】~能楽研修2~
日ごろより国立劇場養成所をご支援くださり、誠にありがとうございます。
国立劇場各館で行われている伝承者養成事業について、皆様にもっと知っていただけますよう、日々の研修の様子などをご紹介してまいります。
今回は「能楽研修」です。
~能楽研修~
前回のご報告では、昨年春~秋頃までの様子をお伝えしました。
今回は、昨年9月から新しいステップに進んだ12期生を中心に、現在に至るまでの能楽研修の活動をご報告いたします。
令和5年9月。
◇大鼓方専攻・中村天海
「学んだことをしっかり身につけていけるよう、一生懸命頑張ります。」

「ご指導いただくこと一つひとつを疎かにすることなく、基礎を大切にお稽古を続けていく所存です。」

◇狂言方専攻・奥悠輔
「まずは身体づくりと声を意識し、先生のご指導を一言一句聞き逃さぬ様、集中して稽古に励んでいきたいと思います。」

・修了者も大活躍!
能楽研修修了者も、引き続き活躍しています!
秋には、お茶の水女子大学と日本芸術文化振興会の連携事業「日本の伝統芸能」講座の能楽バックステージツアー・ワークショップが行われました。
講師のうち、岡本はる奈さん(小鼓方観世流・写真左上)と内藤連さん(狂言方和泉流・写真右)は第8期能楽研修修了者です!
学生のみなさんには、シテ方・小鼓方・狂言方の3つを体験していただきました。
真剣に動きを真似したり、時には笑い声が起きたりと、楽しんでいただけたようです。

また、ある日。
12期の大鼓研修をのぞいてみると…?
専科では先生と研修生が一対一でお稽古しますが、この日は先生のお声がけで、10期修了者の小鼓方幸清流・寺澤祐佳里さん(写真中央)も加わってのお稽古でした!
研修生は、先輩の掛け声が入るなど普段とは全く違う雰囲気に緊張したそうです。

・各公演も実施
1月~3月には、若手能楽師たちによる各養成公演も実施しました。
1月20日(土)は、第32回大阪若手能。
公演前に行われた事前講座では、各演目のシテ(主役)が見どころなどを分かりやすく解説し、こちらにも多くのお客様にご参加いただきました。

翌月2月23日(金・祝)には、第32回東京若手能を開催しました。
厳しい寒さの中、多くのお客様にご来場いただきました。
写真は、能「鐘馗」後シテで使用した能面、小癋見(こべしみ)。
国立能楽堂所蔵の江戸後期の作品です。時にはこうして資料を舞台で使うこともあります!

舞台での位置関係を掴む感覚が普段と全く違ったそうです。
新たな経験でまた一歩成長しました。

・12期生の研修風景
どんどん本格化していく12期生の研修。
研修では、楽器の組み方も教えていただきます。
大鼓は「皮締め」にとても力が必要。
調緒(しらべお)という麻紐を少しずつ締めていくと、ギリギリ、という音が!
研修生によると、終盤の小締(こじめ)を締める部分(写真右)が特に大変だそう。
自主稽古にも励んでいます!

4月からは、新年度の研修が開始され、研修2年目に入った12期生。
今年度からは、笛の研修が始まりました。
最初はなかなか音が出ないと言われる笛(能管)ですが、まずは持ち方を教わり、思い切って吹いてみると…音が鳴りました!
もちろん毎回うまくいくわけではないものの、いいスタートを切れたようです。

同月、12期生は稽古会(非公開)にも初めて出演しました。
これまで見学していた舞台にいよいよ上がることになり、研修生たちは緊張の面持ち…。
そんな3名の素謡「経正」を、ご指導いただいている山階彌右衛門(やましな・やえもん)先生が支えてくださり、無事初舞台を終えました。

途中からは普段通り太鼓を組んでいくのですが、新品の調緒は伸びるので、きつく締めるのが大変だったそうです。楽器の手入れも少しずつレベルアップしています!

・今後の予定
今月は、能楽養成公演が2週続けて開催されます。
6月11日に東京で「青翔会」、そして22日には京都で「京都若手能」です。
次代を担う若手能楽師たちへ、皆様のご声援をお願いいたします!
詳細はこちらから
青翔会:https://www.ntj.jac.go.jp/schedule/nou/2024/3415.html
京都若手能:https://www.ntj.jac.go.jp/schedule/nou/2024/3315.html
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
今後とも、国立劇場養成所にご支援・ご声援をよろしくお願い申し上げます。
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
国立劇場養成課の公式X(旧Twitter)(@kokuritsu_yosei)・Instagram(@kokuritsu_yosei22)・
TikTok(kokuritsu_yosei22)でも、随時研修の様子をご紹介しております。
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ
#伝統文化
- 現在
- 61,755,000円
- 寄付者
- 2,861人
- 残り
- 29日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ
#ものづくり
- 現在
- 217,642,000円
- 支援者
- 12,374人
- 残り
- 29日

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける
- 総計
- 679人

鳥サポーター募集中|鳥と人の共生を目指す活動にご支援を!
- 総計
- 38人

より多くの引退馬の幸せな余生を願う|ヴェルサイユ新厩舎プロジェクト
#地域文化
- 現在
- 33,549,000円
- 支援者
- 1,876人
- 残り
- 38日

関蝉丸神社|"百人一首 蝉丸"を祀る神社に人が集える憩いの場を
- 現在
- 2,720,000円
- 支援者
- 149人
- 残り
- 8日

【継続寄付】かにた婦人の村で自立を目指す女性たちへの伴走者募集!
- 総計
- 51人