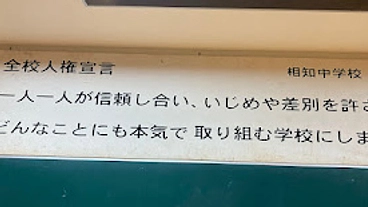寄付総額
目標金額 15,000,000円
- 寄付者
- 1,861人
- 募集終了日
- 2017年9月8日
小児がんの戦いを、いつか仲間と共に歩むきっかけにできたなら
村上 渉さんは、現在24歳。10年前の6月、生存率の低い種類の小児がんにかかったものの、治癒。今は、小児がん経験者としてできることを探している。
自分がしたかったこと、されたかったこと、自分だからこそできること。そのすべてを、未来に託して。今日も一歩、足を踏み出す――

――いつ、どのような小児がんにかかったんでしょうか?
中学3年生のときでした。急性リンパ性白血病という小児がんで、その中でもフィラデルフィア染色体陽性・急性リンパ性白血病という種類の疾患でした。急性リンパ性白血病だったんですけど、骨髄移植が必要だった、という話を聴いています。
こないだ、主治医の先生とランチしたんですが、「今だからいえるけど、渉君の生存率って10%切ってたんだよ」という話をされて。「ウソだろ・・・」とビックリしました。怖かったです。当時、グリベックという抗がん剤が出る前の時代の話なので、(現代の小児がん医療の下で実際の生存率が10%を切っていたかどうかは)何とも言えないらしいのですが。
――入院期間はどれぐらいでしたか?
翌年の3月には退院したので、10ヶ月ぐらいです。ただ、その後(あまり憶えていないんですが)再入院したらしく、高校の入学式だけ出てまた病棟に戻って、というかんじでした。
自分には一つ上の姉がいるんですが、彼女の血液が自分とピッタリだったみたいで。準備のために、同じ病棟で入院して、骨髄移植で助かりました。
その後、小児がん以外にも帯状疱疹だったり筋膜炎だったりと他の病気に罹ってしまって、結構右往左往していました。高校の2学期は丸々休んでしまったんですが、担任の先生が配慮をしてくださって助かりました。
――無菌室での療養はどうでしたか?
無菌室は、ほんと暇でしたね。無菌管理の空間から出ちゃいけないし、無菌室のフィルター装置のそばからそう簡単に動いちゃいけない、と言われていて。現代の無菌室と比べて、当時は全然厳しかったと思います。
僕が入院しているとき、母親が風邪をひいちゃって。それでも、いろいろ着替えとか持って病院にきてくれたんですけど、入れなかったんです。そうでなくても、クリーンカーテンのある廊下までしか来られない、とか。自由に家族にすら会えないという状況で、それなりに寂しい思いもしました。
――何が一番つらかったですか?
骨髄移植の時期、医療用のモルヒネを使っていて、幻覚・幻聴が酷くて頭もほんわりしてしまって。正直、どのぐらいの期間、無菌室にいたのかをあんまり覚えていないんです。顔が暗くて分からないような、知らないスーツの人が見えたり、仲良くしてくれてる看護師さんの声が聞こえて「あの人だ」って分かっているのに顔が見えないということだったり。あとは、寝ようとした時に当時の部活の友達に声を掛けられて「なんだよ」って起きると、誰もいない真っ暗な部屋だった、という経験だったり。寝ようとすると、声が絶対に聞こえるんですよ。だから段々と寝れなくなってしまって、睡眠不足で日中ずーっとぼーっとしてました。
また、抗がん剤を使って「出るかもしれない」と言われていた副作用が総て出てしまって、網膜剥離だったり膵炎だったり、筋膜炎などに苦しめられました。他にも、移植の拒絶反応としてドライアイ・ドライマウスなどがありました。
――「無菌室は、こうあって欲しい」という想いは有りますか?
中学生ぐらいからの子どもにとっては、“無菌室”という場所の存在と名称がすごく怖いんです。何かこう、「そこまで自分は悪くなってしまったのか・・・」という思いにさせられたのを憶えています。
無菌の環境にいなきゃならない、というプレッシャーもありますし、そのプレッシャーを背負いすぎる空間でもないんだという事実を、これから入室する患者さんには伝えて欲しいです。
入院それ自体、心細いものです。それでも、入院生活が日常になってしまうんですね。さらに無菌室は個室だし、それまでの入院生活の日常から切り離されてしまうんです。だから、たとえばそれまで入院病棟で仲良くしてた人たちと交流できなくなってしまう。そうならないように、できる限り寂しくないような環境にして欲しいと思います。

――入院中に出会った方々とは、その後も交流はありますか?
入院中に仲良くなった数人のうち、3人の方が残念ながら亡くなってしまいました。最初、「あの子、亡くなっちゃったみたいだよ」と(親に)言われた時には、けっこうぐちゃぐちゃした気持ちになって。ずっと親御さんも、その子本人も、自分が入院するようになってからたくさん支えてくれた方々でした。しかも、疾患も自分と同じで。だからこそ、「自分も死ぬんじゃないか」という再発の恐怖と死の恐怖とで、一瞬、何も考えられなくなってしまいました。と同時に、「なんで自分じゃなかったんだろう」「自分が死んだ方が良かったんじゃないか」というようなことを考えてしまって、罪悪感のようなものすらおぼえてしまったのを憶えています。
ある方は、ずっと「いつか、医療系の仕事に就きたい」と言っていた方だったので、「自分よりも、彼が生きて仕事に就いた方が、もっとたくさんの人たちを救えたんじゃないか」なんて考えてしまったりしました。
僕も僕で、身体の状態が悪いときと重なってしまって、お見送りの瞬間に立ち会えなかったんです。その時、すぐ駆けつけられなかったのが、悔しかった。その後、自分が大学院に入学したタイミングで、一度ご挨拶をしたいということで、そのときの気持ちをご家族の方に話させて戴きました。
今でも、そのときのご家族とは連絡を取らせてもらっています。ご両親に会いに行くと、「渉君が生きてくれてよかった」と言ってくれます。先々の自分の仕事の話をすると、応援してくれます。だからこそ、というのもあって、彼の分もがんばりたいな、という気持ちにもなりますし、その一方で、彼の遺志を背負えるのかというと、違う気もしますし。今はどこかで、自分のことを見ててくれればいいなあ、と思っています。
――その後の生活で、苦労されたことはないですか?
高校のときとかは、入院してやっとの思いで退院してきたぞ、という気持ちもあったんですが、「自分は普通じゃなくなった」という気持ちと、世の中との隔たりとを凄く感じました。周りは、普通のことができないと“異常”という見方をするし、その人が何故そうなのか(そうなってしまったのか)が分からない存在との関わり方が分からないために排他的に扱う人もいたんですね。
周囲の皆と自分とは、できることが全然違う。しかも、「貴方は優しくされるべき存在の人なんだよ」という趣旨のノーマライゼーションの案内パンフレットのようなものが突然届いたりして。当時のノーマライゼーションと、今現在のそれは違うかもしれないですけど、自分がいろんなところから異常者扱いされているような気持ちにさせられて。半ば死にかけた経験をして社会に出てきたのに「これか」という気分ではありました。
――難しいですね。その人にとっては、「善かれと思って」という思いもあったのでしょうし。
周囲の善意や手助けしたいという純粋な気持ちなのかもしれないんですけど、当事者からすると穿った見方をついしてしまうこともありました。高校生という思春期の時期だということも、少なからず影響していたんでしょうね。
でも、高校生の後半には、「しょうがないか」という様になって来ていて。高校に、すごく気持ちを分かってくれる同級生がいたんですね。暗い話も聞いてもらったりして、「でも、おまえは普通じゃん?」みたいに励まされたりして。
高校受験は、病棟で点滴引きづりながら勉強して、受験しました。入院中は院内学級に転籍して勉強していたんですが、個室では集中できなかったので誰もいないカンファレンスルームを借りて自習をする、という毎日でした。今思うと、よくやってたな、と思います。
――後遺症のようなものはなかったんですか?
ありました。ステロイド薬を使用して治療する経過の中で骨壊死してしまって、腰に段々と痛みが出てきて、大学のころには限界が近づいてきました。
医師の指導で杖をついて大学に通学するようにしたんですが、周囲の反応は様々で。2つの杖をついていくと、「大丈夫?」と言われるし、電車に乗りづらく席を譲るときも舌打ちをされてどいていく、とか。
だからと言って、杖1つでついていくと、どこの学科かも分からないような人たちに「意味あるの?あれ」というような台詞を、自分に聞こえる声の大きさで言われたりして。そういうことが嫌でした。
――そんなことまで…。
自分でも、そろそろ杖がないと もう全然足に力が入らなくなってしまっていて、それですぐ転んでしまう、という状態になってしまっていました。これはもう無理だということで、手術してもらいました。
結果、左股関節を人工股関節に交換しました。最初は歩くのがおぼつかなくて、リハビリテーションで歩く練習とかするんですけど、その歩き方を見て小学生が笑ってくるんですね(笑)。「世の中ってえげつないな・・・」って思った経験でした。
今はもう、立ったり歩いたり、ということについては不自由がないですし、特段困ったことはないです。というより、今の自分が普通になりましたね。自分は、これで生きていこう、という気持ちでいます。

――今後の仕事について
小児がんもそうですけど、難病で入院しているこどもたちの退院してからのフォローというものに、臨床心理士として いつか携わりたいと思います。臨床心理士になって、緩和医療を学べるような入院病棟に勤めたいです。そして、緩和ケアの在り方を身に着けて、いつか小児医療の現場で、僕の様な立場で関わる心理士のスタイルを確立出来たら良いな、と思ってます。
入院病棟に属したいという気持ちが何故あるかというと、「呼ばれたら関わります」というスタンスではなく、「すぐそこにいる」という立場で関わりたいためです。それは、こどもにとって気軽に、気楽に接することのできる存在でありたい、という想いがあるためです。
いつか小児医療の現場で、できれば小児がん拠点病院の現場で、心理の立場として携わりたいです。
――何故、臨床心理士なんですか?
もともと、「心理って、楽しそうだな」と、中学生のころから漠然とした興味がありました。小児がんになってからはこの仕事に向けられる気持ちが強くなって、原体験が基になって、この仕事を目指そうという気持ちが固まりました。
子どもでも子どもなりに、思うところが多くあった少年時代でした。いろいろありましたが、自分の気持ちを話せる場所が全然無かった、というのがつらかったです。家族は入院病棟でできるママ友たちと話せたり、父親はブログを書いたりすることができて“外の世界”との接点があったと思うんですね。
ただ、自分が、自分なりに話せる場所ってそうはなくて。家族は家族でしこたま心配していましたし、医師・看護師は「話は聴くよ」と言ってくれてましたけど、忙しいじゃないですか。で、いざ胃痛が激しくなった時期になって理由が分からずに「心因性かもね」ということになって、「じゃあ話を聴いてくれる人を呼んでくるね」という説明を受けて精神科医が飛んできたんです。
自分としては、怖いじゃないですか(笑)。‟精神科“っていう名前、響きに、「自分、おかしくなっちゃったのかな…」なんて不安になったりして。“精神科”という立場の人から「何でも話聴くからね」と言われたんですけど、「ああ、俺もう何も話せる気がしない」って思ってしまいました。
――どうして話せなかったんですか?
自分は、しっかりとした場を設けて、ちゃんとお話がしたい、という訳じゃなかったんです。ちらっと、こう、「こういうのがつらいんだよね~」ぐらいのことが話せたら、別に良かったんです。正直、『ガチ勢』が来ちゃったな、っていう気持ちになりました。
やっぱり、病気のことが話せる存在が欲しかった、というのが大きかったんでしょうね。それでも、同じ病室の友達とか、看護助手のお兄さんとか、気兼ねの無い関係性で話せる人の存在に救われたのを憶えています。
退院した後も、例えば、自分がつらいこと/つらかったことを周りに話すと、なぜかみんな“ごめんね”って言うんです。でも、誰も悪くないはずじゃないですか。泣いてしまう人もいて。気持ちはありがたいのですが、そうすると本人としては余計話しにくくなってしまう。そこをサポートできるような存在に、自分はなりたいです。

――今のお気持ちは。
もう10周年になるんだな、と思うと、感慨深いです。でも、『生き残った』訳じゃないんですよ、ただ『生きてきた』だけで。よく、小児がん経験者のことを“小児がんサバイバー”っていうじゃないですか。その単語の響き、自分としては結構腑に落ちないんです。
死線を潜り抜けて今ここにいる、という意味ではそうだと思います。ただ、自分が入院中にしていたことと言えば、ベッドで寝っころがって、飲めと言われた薬を飲み、点滴しろと言われた薬を入れ、ただただ指示に従っていただけです。何かしら僕の身体の中で戦っていたものはあったと思いますが、それは僕自身の意志だった訳ではないんですよ。
気持ち悪い、身体が痛い、ということを訴えはしますけど、それで治療を中断するかと言えば、そのことで入院生活が長引くぐらいなら「構わないので、そのまま続けて下さい」という覚悟は、できていました。
子どもたちは骨髄移植や、その後の無菌室での生活など、大変な治療をして病気と戦っています。その治療が終わっても、晩期合併症という、別のベクトルの戦いもあります。僕一人の人生が誰よりもつらいものかというと、それも違うとは思いますけれど、それでも小児がんの子どもたちのこのような戦いを、少しでも知ってほしいと思います。そして、できれば、一緒に戦ってほしいな、と思います。
――小児がん医療へのこだわりについて
小児がんへのこだわりとしては、ずっとそればっかり考えてきたように思います。小児がんに罹った過去があったからこそ、今こうしてここまで来ていると思うんですよ。なったからこそ、という気持ちもあります。
去年、「小児がん看護学会で経験者の立場として話して欲しい」と、昔お世話になった看護師さんに依頼をされました。その時、学会で久しぶりに当時の主治医と再会することになったんです。
「昔は、医者と患者の関係だった。そうじゃない関係で、これからは会えるね。」って言われたことが、すごくうれしかったですね。ずっとお世話になった先生からそう言ってくれたことが、これほど嬉しいことだったなんて。僕、生きてて良かったなぁって思ったんですよ。

(小児がんには)ならなくても良かった経験だったと言えばそれまでですし、また違った人生を歩めたはずだろうな、なんて思いますけど。
それでも、もうなってしまった訳なので。折角の経験をしたんだから、何かしらのかたちで世の中に貢献できたら良いな、と思ってます。
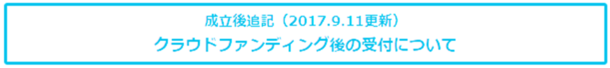
クラウドファンディグでのプロジェクト期間は終了いたしましたが、まだまだご理解・ご支援の輪の広がりを感じております。そして、一人でも多くの方々の願いのとどく企画にできればと思っております。 小児がんと戦うみんなの願いである「無菌室」の新設に、引き続き力をお貸しください。
▼お申し込みはこちら ※今年度中、もしくは資金調達の目途が立ち次第、募集は終了致します
今後とも、国立成育医療研究センターを何卒よろしくお願いいたします。
○こんな記事も読まれています
- ある日突然「がん」を告知された子どもたちは、何に苦しみ、どんな夢を見るのか
- すべての小児がんの子どもが治癒しますように(松本 公一)
- 小児がんの戦いを、いつか仲間と共に歩むきっかけにできたなら
- 写真展 『 I 』(Bukatsudo ギャラリー)のご案内
- 小児がんと戦う、みんなの願い。不足する無菌室をつくろう!(松本公一国立成育医療研究センター小児がんセンター長) - クラウドファンディング Readyfor
ギフト
3,000円

小児がんの子どもの願いを一緒に
■小児がんセンターサポーターに任命:皆さまにはサンクスメールと無菌室(クリーンルーム)稼働の報告メールをお送りします
■御礼状・ 寄附金品領収証明書の送付
- 申込数
- 1,104
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2018年2月
10,000円

小児がんの子どもの願いを一緒に
■小児がんセンターサポーターに任命:皆さまにはサンクスメールと無菌室(クリーンルーム)稼働の報告メールをお送りします
■御礼状・ 寄附金品領収証明書の送付
- 申込数
- 557
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2018年2月
3,000円

小児がんの子どもの願いを一緒に
■小児がんセンターサポーターに任命:皆さまにはサンクスメールと無菌室(クリーンルーム)稼働の報告メールをお送りします
■御礼状・ 寄附金品領収証明書の送付
- 申込数
- 1,104
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2018年2月
10,000円

小児がんの子どもの願いを一緒に
■小児がんセンターサポーターに任命:皆さまにはサンクスメールと無菌室(クリーンルーム)稼働の報告メールをお送りします
■御礼状・ 寄附金品領収証明書の送付
- 申込数
- 557
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2018年2月

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ
#ものづくり
- 現在
- 216,904,000円
- 支援者
- 12,300人
- 残り
- 29日

1頭1頭と向き合い続けるために。引退馬たちに安心安全な新厩舎建設へ
- 現在
- 73,896,000円
- 支援者
- 6,381人
- 残り
- 32日

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける
- 総計
- 679人

入院する子どもたちを笑顔に!ファシリティドッグ育成基金2025
#子ども・教育
- 現在
- 6,818,000円
- 支援者
- 543人
- 残り
- 25日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ
#伝統文化
- 現在
- 59,605,000円
- 寄付者
- 2,851人
- 残り
- 29日

「合う肌着がない」難病の娘に笑顔を!家族で開発、超細身キッズ肌着
- 現在
- 1,538,000円
- 支援者
- 228人
- 残り
- 18日

ひとつの心室で生きていく。フォンタン手術の患者をみんなで支援したい
- 現在
- 3,409,000円
- 寄付者
- 171人
- 残り
- 29日