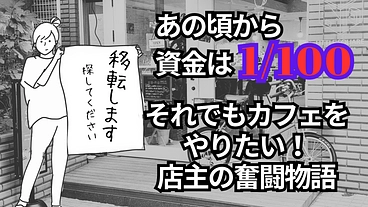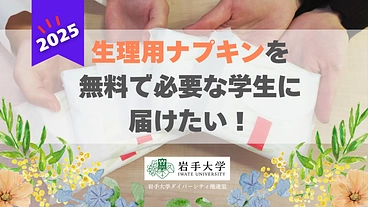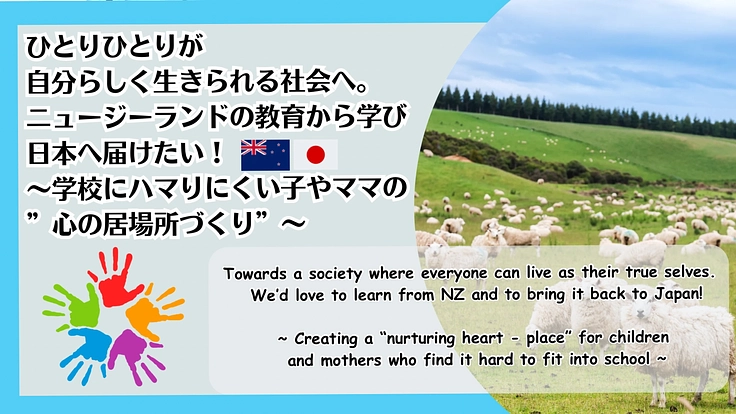
支援総額
目標金額 1,500,000円
- 支援者
- 133人
- 募集終了日
- 2025年4月30日
Day24 未来を切り拓く学びの場
おはようございます!寿里です。
これまで教育現場で働き、また子育てをしてきた中で、私は本当の意味で子どもたちが幸せに生きるためには、どのような関わりが大切なのかという問いについて考えてきました。
日本では、自己肯定感を「どうやって高めるか?」が課題だとされますが、ニュージーランドでは「そもそも低くならないような教育や社会の仕組み」があります。
そのため、日本のように「自己肯定感を高めよう!」と強調することはあまりありません。なぜなら、子どもが自己肯定感を持つことが当たり前の環境が整っているからです。
では具体的にどのような教育や環境があるのかについてまとめてみました。
🔶幼児教育カリキュラム「テファリキ」
テファリキは、子ども一人ひとりの個性や主体性を尊重し、自己肯定感を育むことを重視しています。具体的には、子どもたちが自分の興味や関心に基づいて学ぶ環境を提供し、成功体験を積み重ねることで自信を深めるよう支援しています。
幼少期から「あなたはあなたのままで素晴らしい」というメッセージを伝えます。
学校教育では大きくこの4つに分けて比較していきます。
「学びの主体性」「評価のあり方」「先生の役割」「学校の環境」
🔶学びの主体性:先生主導 vs. 子ども主体
日本では、先生が教科書の内容を決められた通りに教え、子どもたちはそれを覚えるという「一斉指導」が基本です。先生が知識を与えるスタイルが中心で、子どもが学び方を選ぶ機会は少ないです。
ニュージーランドの学校では、子どもたちが自分の興味に基づいて探究する「Inquiry Learning(探究学習)」がよく行われます。
例)「環境問題」に興味がある子は、海洋プラスチックの影響について調べて発表。
「料理」に興味がある子は、世界の食文化について学び、レシピを考案してクラスで試食会など、子どもが自らテーマを決め、リサーチ・発表までを主体的に行います。
🔶 評価のあり方:テスト重視 vs. プロセス重視
日本では、テストの点数や偏差値などの「数値評価」が非常に重要視され、学習の成果はテストで測られることがほとんどです。そのため、授業の目的が「良い点を取ること」になりがちです。
ニュージーランドでは、子どもがどのように学び、どのように成長しているかという「プロセス」が重視されます。テストの点数だけではなく、プロジェクト型学習(PBL)やプレゼンテーションを通して、自分の意見を表現できるかどうかが評価の基準になります。
💗1年間現地の高校に留学していた娘(高1)の年度末のレポートを見て驚きました。テストのスコアよりも、人間性や個人の成長、パーソナリティを肯定してくれる言葉に溢れていました。こんなに自己肯定感が上がるレポートは初めて見ました!
🔶 先生の役割:知識を伝える vs. コーチング型のサポート
日本の先生は、主に「教える人」としての役割を担い、カリキュラムに沿って知識を伝えることが中心です。また、部活動の指導や事務作業も多く、忙しさが問題になっています。
ニュージーランドの先生は、子どもが学ぶプロセスをサポートする「ファシリテーター」のような役割を担います。子どもたちが自ら考え、学べるように導くことが求められます。コーチング的な関わりを大切にし、子どもとフラットな関係を築くことが特徴です。
💗Teacher’s dayという、先生だけが登校する日があると聞きました。先生が大切にされる環境も素敵ですよね!
🔶 学校の環境:統一された学び vs. 多様性の尊重
日本の学校は「全員が同じように学ぶ」ことを重視し、授業の進め方や学習のペースも統一されています。また、制服や校則が厳しい学校も多く、個性よりも集団行動が求められることが多いです。
ニュージーランドでは、子どもの多様性を尊重する文化があり、学習スタイルや服装の自由度も高いです。また、教室のレイアウトも自由で、個々の特性に合わせた柔軟な環境づくりが進んでいます。
💗規則でがっちり固めなくても、秩序を守るという生徒に対する信頼の表れなのだと思いました。
🔶本当の意味で子どもたちのためになる教育とは?
比較してみると、日本のあたり前に疑問を持つことが出来ると思います。
自分に合った学びのスタイルを見つけられたり、学びたいことに没頭できたり、自分の個性に気づくプロセスが学校教育の中に組み込まれていたら、これほど素晴らしい環境はありませんよね。
少なくとも、学校が合わない子どもたちが 「学校に通えない自分に対して後ろめたさを感じる」と自己評価を下げることのないように、もっと柔軟で多様な学びの場があるべきだと強く願っています。
私たちにできることは何か? その答えを、このプロジェクトを通して形にしていきたいと思います。
そのためにも、皆さんのご協力・ご支援が必要です!
引き続き、応援よろしくお願いいたします!
------------
Day 24: A Learning Environment to Shape the Future
Good morning! This is Juri.
In Japan, the focus is often on "how to boost self-esteem," but in New Zealand, the system is designed to prevent self-esteem from getting low in the first place. Therefore, there is less emphasis on actively raising self-esteem, as it is taken for granted that children will have it in a supportive environment.
Here’s a look at how New Zealand's educational system fosters this:
🔶 Early Childhood Curriculum "Te Whāriki"
Te Whāriki emphasizes respecting each child's individuality and fostering self-esteem. Children learn based on their interests and experiences, and success builds their confidence. From a young age, they are taught, "You are wonderful just as you are."
Key Areas of Comparison in Education:
🌟Self-Directed Learning:
In New Zealand, children engage in "Inquiry Learning," where they explore topics they are passionate about. This contrasts with Japan’s teacher-led, textbook-based approach.
🌟Evaluation Approach:
While Japan focuses on test scores, New Zealand emphasizes the learning process. Assessment often includes projects and presentations where children express their opinions, valuing growth over numbers.
🌟Teachers’ Role:
In Japan, teachers are primarily knowledge deliverers. In New Zealand, teachers are more like facilitators, guiding students to think critically and learn independently, building flat, supportive relationships with them.
🌟School Environment:
Japan values uniformity and discipline in school life, with strict rules and an emphasis on group behavior. In New Zealand, diversity is celebrated, with flexible learning environments that cater to individual needs and learning styles.
🔶 What does truly supportive education for children look like?
Looking at these differences, we can question some of Japan’s norms. A system that helps children find learning styles that suit them, allows them to pursue what they are passionate about, and encourages them to discover their unique qualities would create an incredible educational environment.
I believe it is essential that we create more flexible and diverse learning spaces, so that children who struggle in traditional schools don’t feel like failures.
What can we do? Through this project, we aim to find that answer and make it a reality.
We need your continued support to make it happen. Thank you!
リターン
3,000円+システム利用料

感謝のメール Thank-you e-email
⚫︎感謝のメールをお送りします。
- 申込数
- 68
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2025年5月
10,000円+システム利用料

現地レポ(活動報告PDF)activity report (PDF)
⚫︎感謝のメールをお送りします。⚫︎活動報告をお送りします。
- 申込数
- 46
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2025年10月
3,000円+システム利用料

感謝のメール Thank-you e-email
⚫︎感謝のメールをお送りします。
- 申込数
- 68
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2025年5月
10,000円+システム利用料

現地レポ(活動報告PDF)activity report (PDF)
⚫︎感謝のメールをお送りします。⚫︎活動報告をお送りします。
- 申込数
- 46
- 在庫数
- 制限なし
- 発送完了予定月
- 2025年10月

「ちいさな音楽家サポーター」プログラム マンスリー(毎月寄付)会員
- 総計
- 78人

障がい者がより豊かに生きられる社会を!みらせんサポーター募集!
- 総計
- 37人
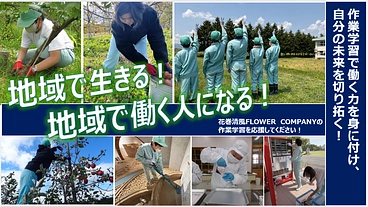
「地域で生きる!地域で働く人になる!」生徒たちに豊かな職業体験を
- 現在
- 1,103,000円
- 支援者
- 127人
- 残り
- 10日

「働くことを諦めない」精神科医療を。札幌からの挑戦
- 現在
- 619,000円
- 支援者
- 38人
- 残り
- 15日

心理専門職による「心のケア」を、必要な人に無料で届けたい
- 総計
- 11人

重症児や医療的ケア児も思い切り挑戦できる!「可能性育む」療育拠点を
- 現在
- 270,000円
- 支援者
- 28人
- 残り
- 22日