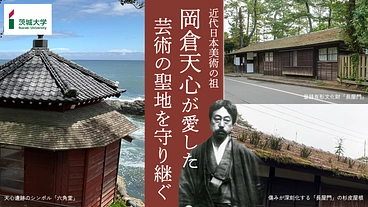クラウドファンディング終了まで残り4日!
舞妓さんのかんざしなどに使われている日本の伝統技術をご存知ですか? 「つまみ細工」と呼ばれる江戸時代から伝わる技法で、薄絹の「羽二重」を正方形に小さく切り、これを摘んで折りたたみ、…
もっと見る
支援総額
目標金額 1,000,000円
舞妓さんのかんざしなどに使われている日本の伝統技術をご存知ですか? 「つまみ細工」と呼ばれる江戸時代から伝わる技法で、薄絹の「羽二重」を正方形に小さく切り、これを摘んで折りたたみ、…
もっと見る日本人にとって特別な色である藍。 日本の伝統色である藍色は東京オリンピックのエンブレムデザインにも用いられ、サッカー日本代表のユニホームに使われた「サムライブルー」もルーツは藍色で…
もっと見る▼小川和紙とは 緑豊かな山々に囲まれた小川盆地、その山あいを槻川や兜川の清流。 都心に比較的近いという地理的条件と、原材料となる資源が豊かだったことが、伝統工芸の歴史を物語ってきま…
もっと見る▼淡路瓦の歴史 淡路瓦は、幾多の時代と社会の変遷のなか、400年の歴史を刻んだ伝統工芸的地場産業です。 その間、先人から子々孫々へと受け継がれ、知恵と美意識に磨かれた瓦の形状は、実…
もっと見る国生みの島と言われる淡路島。淡路島は古くから日本の香りのふるさととも言われています。 今回は淡路島にある淡路梅薫堂さんにお伺いし、お線香を作る体験をした様子をまとめています。体験や…
もっと見る東京都新宿区にある匠木版画工房「ふれあい館」。ここでは職人さんによる実際の作業の様子を見せて頂きながら、日本の伝統工芸である版画について学びました。 ▼浮世絵とは(歴史) 浮世絵彫…
もっと見る▼「つまみ細工」とは(歴史) 「つまみ細工」とは江戸時代から伝わる技法で、薄絹の「羽二重」を正方形に小さく切り、これを摘んで折りたたみ、組み合わせることによって花や鳥の文様をつくる…
もっと見る▼日本の色「藍」と藍染 昔から藍染は広く民衆に親しまれてきました。 のれん、手ぬぐい、浴衣、風呂敷など、藍色の布製品は古くから日本の暮らしに密着してきました。 日本人にとって特別な…
もっと見る▼江戸切子とは(歴史) わが国での製作は天保5年(1834年)に、江戸大伝馬町のビードロ屋加賀屋久兵衛が 金剛砂を用いてガラスの表面に彫刻したのが初めてと伝えられています。 明治6…
もっと見るはじめまして、田中千晶(Tanaka Chiaki)です。 私のプロジェクトページをご覧いただき、ありがとうございます。 『伝統工芸品』は細かな作業一つ一つに意味があって、造り手か…
もっと見る5,000円

①寄木細工 ②小田原漆器 ③鎌倉彫 の伝統工芸師さんから、直筆のお手紙をお届けします。
伝統工芸師さんの温かな思いを身近に感じることができます。
(上記3名の工芸師さんから1名お選びいただけます)
10,000円

感謝の気持ちを込めた手紙と、伝統工芸品1品(小物)をお送りいたします。
(工芸品は①寄木細工 ②小田原漆器 ③鎌倉彫 のいずれかランダムでのお届けとなります。)
5,000円

①寄木細工 ②小田原漆器 ③鎌倉彫 の伝統工芸師さんから、直筆のお手紙をお届けします。
伝統工芸師さんの温かな思いを身近に感じることができます。
(上記3名の工芸師さんから1名お選びいただけます)
10,000円

感謝の気持ちを込めた手紙と、伝統工芸品1品(小物)をお送りいたします。
(工芸品は①寄木細工 ②小田原漆器 ③鎌倉彫 のいずれかランダムでのお届けとなります。)