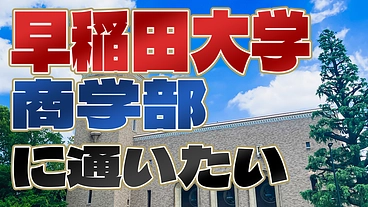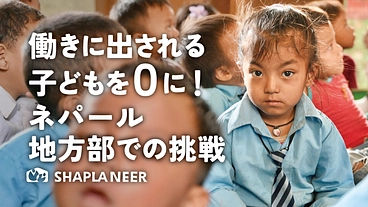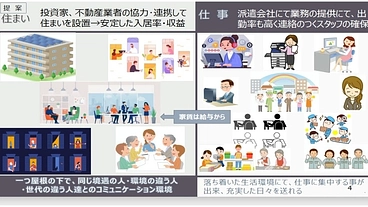支援総額
目標金額 200,000円
- 支援者
- 22人
- 募集終了日
- 2014年8月9日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ
#ものづくり
- 現在
- 223,646,900円
- 支援者
- 13,108人
- 残り
- 27日

「合う肌着がない」難病の娘に笑顔を!家族で開発、超細身キッズ肌着
#子ども・教育
- 現在
- 1,607,000円
- 支援者
- 240人
- 残り
- 16日

天草への情熱が生む | フィカス(無花果)が香る芳醇なクラフトジン
#地域文化
- 現在
- 710,000円
- 支援者
- 25人
- 残り
- 49日
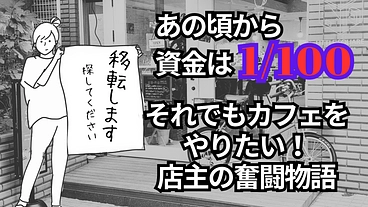
あの頃から資金は1/100!それでも心を癒す小さなアジトを守りたい
#まちづくり
- 現在
- 110,000円
- 支援者
- 5人
- 残り
- 38日

歩けるのがうれしい失明犬の光ドッグバンパー製作費の継続支援をぜひ!
#医療・福祉
- 総計
- 5人
プロジェクト本文
パフォーマンスでテキスタイルの魅力をもっと多くの人に知ってほしい
初めまして!私たちは、多摩美術大学でテキスタイルを学ぶ3年生です。「テキスタイル」は、あまり知られていない言葉ですが、実は誰もが毎日触れている、服や、カーテンや、電車のシート、つまり「布」で作られているもの全てがテキスタイルです。こんなにも身近な存在なのにも関わらず、この言葉を知っている人は少ないと思います…。
そこで、私たちはその魅力や可能性をもっと広めたい思いから、テキスタイルパフォーマンスを企画しました。11月に行われる「多摩美術大学芸術祭」にて、舞台、衣装、演出全てをテキスタイル専攻3年生を中心とする学生総勢140人で作り上げた、「テキスタイルパフォーマンス2014」を公演致します!
しかし、パフォーマーのための衣装が50体の制作にかかる材料費が20万円程足りていない状況です。どうか皆様のお力をお貸しください!

(過去公演の様子)
テキスタイルとは?
テキスタイルは、太古から人の手によりつくられ人間の心身と生活を包み育んできた人々をつなぐ共通の営みです。世界中のあらゆる民族が、風土に根ざした繊維素材と技術によりそれぞれの文化を創出しています。今日、身近な衣生活や住空間にとどまらず、車両内装・産業資材、医療素材から宇宙開発の素材として様々な場所で用いられ、その可能性は広がり続けています。

(授業は基本制作を行っています、この画像は染めの授業です)
私たちにとって、テキスタイルパフォーマンスはなくてはならない存在
私たちテキスタイル専攻にとって、テキスタイルパフォーマンスはなくてはならない存在であり、代々3年生有志が受け継いでおり、今年で23回目となります。テキスタイルデザイン専攻伝統の催しとして、毎年 2000 人近くのお客様にご来場いただいてお り、昨年度は 2700 人もの方にご覧いただきました。
近年では海外からも注目され、2012 年度のテキスタイルパフォーマンスはフィンランドのアアルト大学で開催された 「FIBER FUTURES Japan’s Textile Pioneers 展」にて展示とプレゼンテーションを 行いました。

(過去公演の様子)
人と布の関係について深く考察し、表現する場としてのパフォーマンスショー
「テキスタイルパフォーマンス」はいわゆる「ファッションショー」とは一線を画するもの です。テキスタイルについて専門的に学んでいる私たちだからこそできる表現、技法を 駆使し、テキスタイルについて多くの方に知ってもらいたいという気持ちからショーを 行っております。
日頃、私たちは「染め」「織り」「プリント」などの専門技術を学び、 あらゆる繊維素材を用い、テキスタイルの可能性を追求しています。そうした学業研究の中で得られた技術や知見をもとに、人と布の関係について深く考察し、表現する場としてこのパフォーマンスショーを行います。芸術祭という学外からもたくさんのお客様に 来て頂ける貴重な機会に、このショーを行うことで、テキスタイルのもつ多くの可能性と魅力を伝えたいと考えています。

(過去公演の様子)
引換券について
引き換え券については、3000円〜私たちが生地から手作りしたオリジナルグッズをプレゼント致します!!テキスタイル専攻だからこそできる手作業を、お届けいたします。
5000円〜会場で配布するパンフレットにお名前を掲載させていただきます。(ご希望でない場合は掲載致しません)
10000円〜会場ご招待チケットをプレゼントいたします。私たちの努力の成果を是非ご覧下さい!!(30000円〜はチケットの日時指定が可能になりますので、お時間のよろしい日に是非お越し下さい。)


(過去公演の様子)
あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!
プロフィール
私たちは多摩美術大学でテキスタイルを学んでいます。あまり知られていない、テキスタイルをもっと身近に感じて欲しい、という思いで活動しています。
あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!
リターン
3,000円

サンクスレター
生地から手作り!オリジナルコースター
- 申込数
- 0
- 在庫数
- 制限なし
5,000円

サンクスレター
会場で配布するパンフレットに名前掲載(ご希望でない場合、掲載は致しません)
オリジナルコースタープレゼント!!
- 申込数
- 8
- 在庫数
- 制限なし
3,000円

サンクスレター
生地から手作り!オリジナルコースター
- 申込数
- 0
- 在庫数
- 制限なし
5,000円

サンクスレター
会場で配布するパンフレットに名前掲載(ご希望でない場合、掲載は致しません)
オリジナルコースタープレゼント!!
- 申込数
- 8
- 在庫数
- 制限なし
プロフィール
私たちは多摩美術大学でテキスタイルを学んでいます。あまり知られていない、テキスタイルをもっと身近に感じて欲しい、という思いで活動しています。